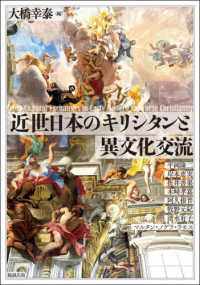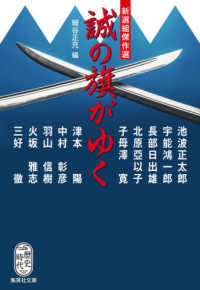- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 哲学・思想
- > 構造主義・ポスト構造主義
内容説明
その死から20余年、いま明かされる最晩年のバルト、その思索の光芒!ギリシア正教の聖なる場、アトス山の修道院に見られる“共生”の形態から出発、バルト自ら愛した多彩なテクストの分析をとおして「ともに生きること」が主体にもたらす経験の多様性とその意味の解明が、スリリングに、ときには倒錯的な魅惑とともになされてゆく。
目次
いかにしてともに生きるか
1977年1月12日の講義
1977年1月19日の講義
1977年1月26日の講義
1977年2月2日の講義
1977年2月9日の講義
1977年2月16日の講義
1977年3月2日の講義
1977年3月9日の講義
1977年3月16日の講義〔ほか〕
著者等紹介
バルト,ロラン[バルト,ロラン][Barthes,Roland]
フランスの批評家・記号学者。1915年、シェルブールに生まれる。幼年期を南西部バイヨンヌで過ごしたのち、パリに移る。47年ごろから新聞や雑誌で批評活動をはじめ、数々の著作を発表。60年からパリの高等学術研究院の教職につき、76年、コレージュ・ド・フランスの教授に就任、文学の記号学の講座を担当した。80年、交通事故に遭い3月26年に逝去
野崎歓[ノザキカン]
1959年生まれ。東京大学大学院総合文化研究科助教授(言語情報科学専攻)。専門は、フランス文学、映像文化論。『ジャン・ルノワール 越境する映画』で、サントリー学芸賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きいち
9
別々の個人が自分のリズムを守ったまま、ともに生きるということが可能か?それをファンタジーといいながら、中世ギリシャの修道院の話を中心にいくつかの小説やドキュメンタリーを使い例のアルファベット順で述べられると、規則の自己増殖も個人の暴走も止められそうな気がしてくる。◇最初はぶっちゃけわけわからなすぎて心配したが、途中からコツがつかめたように思う。それもこれも、密室に監禁された女のエピソードのおかげだ。◇現代社会では「減速の技法こそ進歩的」だからこそのこの方法か。やっと得心いった気がする。2013/05/18