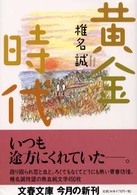出版社内容情報
どんな人にもトラウマはある。まずはそのいたみを自覚し、こじらせてしまわないことが肝要だ。トラウマのメカニズムや和らげる術を豊富な事例から紹介する。
内容説明
どんな人にもトラウマはある。まずはそのいたみを自覚し、こじらせないことが肝要だ。明日も無事に生き延びるため、トラウマのメカニズムやいたみに向き合いながら和らげる術を豊富な事例から紹介する。
目次
第1章 トラウマ反応で起きること
第2章 トラウマとは何か―そのメカニズム
第3章 トラウマ反応という心の働き
第4章 トラウマと向き合う―トラウマに苦しんでいるあなたに
第5章 からだを通して、トラウマを癒す
第6章 僕の「旅」治療
第7章 安全感・安心感を提供する―周囲の人にできること
最終章 ヒロシマ―僕のトラウマから、僕らのトラウマへ
おわりに―過酷な体験を共有すること
著者等紹介
青木省三[アオキショウゾウ]
1952年広島市生まれ。岡山大学医学部卒業。川崎医科大学精神科学教室主任教授を経て、現在、公益財団法人慈圭会精神医学研究所所長。川崎医科大学名誉教授。臨床精神医学、特に精神療法、思春期青年期を専門としている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
morinokazedayori
27
★★★★著者は精神科医。とても優しく易しい言葉で、トラウマとその癒しかたについて書かれている。トラウマについてもっと深い構造的なことが知りたくなったが、読み進めるうち、日々の小さな、周りの人との積み重ねこそがトラウマを癒してくれることに気付き、満たされた気分になる。2021/05/19
tenori
23
トラウマと呼ばれる心の傷についてメカニズム、向き合い方、周囲の支援策などを簡潔に集約。「心の傷から流れ出す血は目に見えない」だけに対処は難しい。癒しと言う単語の乱発を批判しつつも、日々いたみを自覚しながら、こじらせることなく生きること(癒しの意味)を説く。一方で自らの過酷な体験を周囲に伝えることが抑止力を生むきっかけになり、話すことでトラウマを解放できる可能性についても言及。個人のトラウマの伝承がヒトの歴史を作ってきた=多くのいたみの上に今が成り立っていると考えると感慨深い。2020/05/15
通りすがりの本読み
18
まるでカウンセリングを受けているみたいな優しい本でした。内容も難しいところがなく読みやすくトラウマ発生のメカニズムからどのように向き合って癒していくか、トラウマを癒すのに劇薬で一気に治すのではなくゆっくりと癒えてほしいという著者の思いが溢れています。日常のちょっとした事がトラウマを癒すのにいいんだなと思いました。そして人と話すこと関わることが大切であるとわかりました。2024/08/24
ハイちん
18
トラウマを克服するというのは最近の僕のテーマだ。人間関係がうまくいかなかった経験からか、仕事をしていると、その頃の記憶が蘇り、職場の人間どもに対する不信感や激しい怒りが湧き出ていた。良好な人間関係を築くどころか仕事にならなかった。結局仕事を辞めた。退職後は自分はまともな人間関係を築けない社会不適合者だと自分を責めた。そんな中、職業相談の先生と出会い、何度も通ううちに仕事をしたいと思うようになった。だからこの本に書かれている「トラウマは外部との関係で癒える」という助言は実感として理解できる。2021/10/30
riviere(りびえーる)
18
新刊の新書版なので手に取った。思春期青年期をとりわけ得意とする精神科医による、若かりし頃の著者の体験も描かれている心暖かい一冊。バリバリの専門家向けというよりは本人や家族、そして生活場所や地域で支援する人向けの印象。熱く語りかけてくる人でもなく、ドライでもなく、「しつこくない暖かさ、押しつけがましくない、ほんのりとした暖かさ」で支援を、という表現には同感。2020/05/31