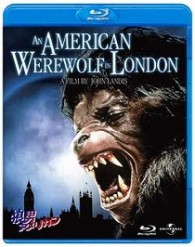出版社内容情報
一握りの人間に付き従う大勢順応の国民性はいったいどこから生まれたのか? 柳田國男とその弟子たちが民俗学の成果を結集してその問いに挑む。
内容説明
日本各地の伝統行事や習俗、伝承を集めるのが目的と思われがちな民俗学。しかし民俗学の父・柳田國男が目指したのは、民俗調査によって日本人の国民性を形成したものを明らかにし、現在起きている問題を解決する一助とすることだった。官僚として人生のキャリアをスタートさせた柳田は「なぜ選挙のたびに不正が行われるのか」という問題意識を常に持っていた。柳田は現前の疑問に答えるべく自らの学を展開していく中で、その原因となるオヤカタ・コカタなどの民間習俗に辿り着く。柳田が「世相解説の学」「経世済民の学」と定義した民俗学の立ち位地を鮮明に示す日本人論の白眉。
目次
1 日本人とは
2 伝承の見方・考え方
3 家の観念
4 郷土を愛する心
5 日本人の生活の秩序
6 日本人の共同意識
7 日本人の表現力
8 日本人の権威観
9 文化の受けとり方
10 不安と希望
「日本人」座談会
著者等紹介
柳田國男[ヤナギタクニオ]
1875‐1962。兵庫県に生まれる。幼少年期より文学的才能に恵まれ、短歌、抒情詩を発表。東京帝国大学を卒業後、農商務省、貴族院勤務を経て、朝日新聞社に入社。勤務の傍ら全国各地を旅行し、民俗学への関心を深める。1909年、日本初の民俗誌『後狩詞記』を発表、以後『遠野物語』から晩年の『海上の道』に至るまで多大な業績を遺す(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
うえぽん
CTC
さとうしん
roughfractus02