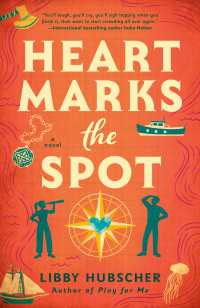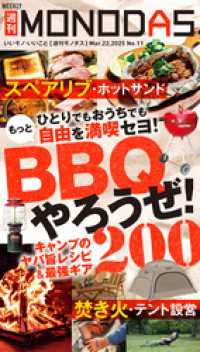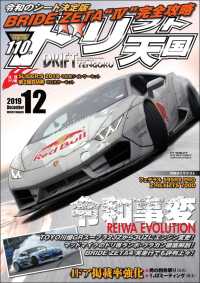出版社内容情報
普通の人びとはナチズムをどのように受け止めたか。とある農村と炭鉱町での証言から、平凡な日常生活がナチ体制に組み込まれていく様をあぶりだす。
内容説明
第三帝国といえば、ゲシュタポの監視のもと恐怖と暴力で国民を支配したイメージがある。しかし、当時を回想する住民証言から現れるのは、ナチズムへの不満や批判ではなく、むしろ正反対の「ナチスの時代はよい時代だった」という記憶だ。ごく平凡な普通の人びとが、ナチズムとは一定の距離をおきながらも、非政治的領域のルートを通じ、政策を支持するようになる。農村ケルレと炭鉱町ホーホラルマルクという、二つの地域での詳細なインタヴュー資料を中心に、子どもや女性までもが、徐々にナチ体制に統合されていった道程をあばきだし、現代のわれわれにも警鐘を鳴らす一冊。
目次
第1章 褐色の農村と赤い炭鉱町(褐色の農村―ケルレ村;すっきりしない状況の成立;赤い炭鉱―ホーホラルマルク;悪い時代のはじまり)
第2章 ヒトラーが政権についたとき(ナチスは外からやってきた;全体としては、がまんできた;たいしたことはなく、なにもおきなかった;もう他人を信用できなくなった)
第3章 民族共同体の夢と現実(記憶に残らない不満と批判;いい時代だった;行ったこともない旅行の記憶;たいていの家でもめごとがおきた;ハンチングはタブーだった)
第4章 ユダヤ人、戦争、外国人労働者(内に向けて発動される人種主義;もったいないという反応;戦争さえなければよかったのに;いまでもそのことを恥ずかしく思う)
著者等紹介
山本秀行[ヤマモトヒデユキ]
1945年神奈川県生まれ。東京大学文学部西洋史学科卒業。東京大学大学院修士課程修了、同大学助手。ハンブルク大学留学、お茶の水女子大学講師、同助教授、同教授。こども教育宝仙大学学長を経て、お茶の水女子大名誉教授。専門は、西洋近現代史、ドイツ史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
marty@もぶおん学
Hiroshi
よしくん
ポルターガイスト
こうず