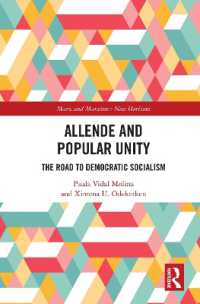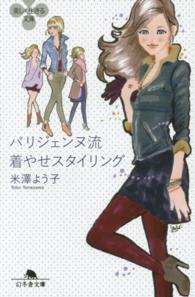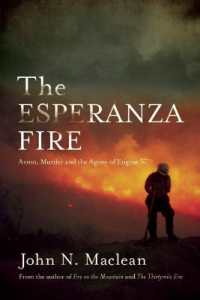出版社内容情報
幕末、内戦の末に賊軍の汚名を着せられた水戸天狗党の戦い。その悲劇的顛末を全篇一人称の語りで描いた傑作長篇小説。
内容説明
尊皇佐幕の藩論統一を巡って、骨肉相食む「内戦」を戦い、二千人とも五千人ともいわれる死者を出した水戸天狗党の乱。敗残の武田耕雲斎、藤田小四郎らは八百余名の残兵を率い、雪と氷の道無き山中、京へ向かう死の大長征を開始した…。維新史最大のタブーに真正面から挑む異色歴史巨篇。
著者等紹介
山田風太郎[ヤマダフウタロウ]
1922年、兵庫県養父郡の医家に生まれる。『甲賀忍法帖』『くノ一忍法帖』などで数々の“風太郎忍法”を生み出し忍法帖ブームをまきおこす。『警視庁草紙』などの明治を舞台にした小説や、『戦中派不戦日記』『戦中派虫けら日記』などの日記文学、『人間臨終図巻』をはじめ死を見つめた著書等多数。1997年第45回菊池寛賞を受賞。2001年、尊敬する江戸川乱歩と同じ、7月28日没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
syaori
61
天狗党の乱を追う歴史物。幕末といえば黒船という脅威を背景に、世のための志を胸に奔走する志士たちが魅力ですが、ここで語られるのはその虚しさ。物語は尊皇、攘夷を問わずその思想を義と信じ純粋にそれに賭けた人々に何も残らなかったこと、高い志同士の対立も外から見たら「人を殺し、きちがいのように駈けまわっている」行為に過ぎないこと、それは「復讐ごっこの反復」を招くことを多角的な視点で描き出します。そのイデオロギーに囚われ固執することの虚しさ恐しさを、どこか艶やかに娯楽性を失わずに描き切る作者の筆を堪能した読書でした。2022/02/03
ちゅんさん
43
天狗党のことは名前ぐらいしか知らなかった、多少創作はあるだろうけどこれがほとんど史実であることに驚く。本当につじつまが合わないことだらけで皮肉で悲惨な話だったけど山田風太郎にかかればこんなに面白い小説になるんだな。それにしても天狗党とはなんだったのか…2021/01/27
№9
42
幕末、水戸藩で吹き荒れた天狗党による争乱の顛末を、その首領である武田耕雲斎の子、15歳の源五郎の視点によって語られる。血で血を洗う陰惨な抗争と京への陰鬱な行軍、そして酸鼻な結末。純粋ともいえる源五郎少年の一人称によって、また維新後30年を経て彼が大人となって振り返る顛末の物語りは、単なる暗黒史物語ではなく、その混迷極まる時代を生き抜かざるをえなかった人々への鎮魂録となっていると思う。本編から得られる感動の源泉は、作者のそうした意図にあると僕は見た。2014/01/30
きょちょ
33
再読本。幕末の水戸藩の内紛・内戦、これほど凄まじいのは日本史上他にないのではないか。動乱期だから、「何でもアリ」である。謀反のつもりはまるでないのに、勝手に「謀反」とされてしまい、頼りとする徳川慶喜からも討伐隊を出されてしまう天狗党。死んでも死にきれないとはまさにこのことだ。維新後、水戸藩から誰も明治政府に重用されないのは、この内戦で人材が全くいなくなってしまったからだ。また、天狗党が京へ上る途中の各藩にとっては、題名通り「魔群の通過」である。天狗党処罰の後の話は感慨深いものがある。 ★★★★ 2017/04/21
キムチ
29
筆者の明治モノがつとに好きな事もあり、思った通りの筆致。特に妻籠通過で藤村の父との絡みは山田節さく裂。文庫解説は好きな関川氏。独特の語りが楽しく、ダブルで楽しめる。ひょんなことから興味を持った天狗党の幕末叙事詩、関川氏曰く現代で同じ行程をこなせば猛烈に苛酷な旅となるようだ。やはり圧巻は根尾川沿いの峠越え、谷汲村から木ノ本、今庄。当時の積雪が少なかった事で行けたとあるが。耕雲斎四子が回想する形を取っているが15歳の眼は今のそれと異なり長けたモノがあろうと推し量れるだけに、読み進むと重苦しい凄惨さが溢れる。2014/12/01