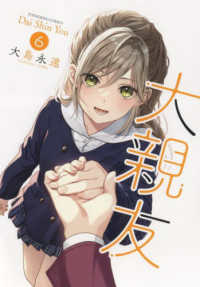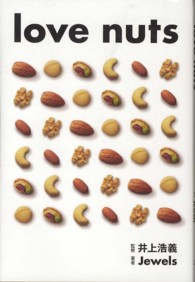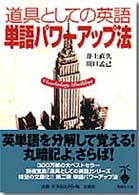出版社内容情報
内容は後日登録
内容説明
「いじめをする子どもは、他人に対する思いやりの心が欠けているのだ」。このように人がある行動をとることの原因を個人の心のあり方に求める「心でっかち」な考えが、私たちの目を曇らせてしまっている。身の周りに潜むそうした罠に陥ることなく、現実を正しく理解するにはどうすればよいのだろうか。社会と個人の関係に鋭く切り込み、問題解決への糸口を探る。
目次
はじめに あなたも「心でっかち」になっていないか
第1章 日本人は集団主義ではなかった
第2章 心でっかちの落とし穴
第3章 心でっかちな文化理解を取り除く
第4章 内集団ひいきはどのようにして生まれるのか
第5章 だれもが皆、心の道具箱を持っている
第6章 心の道具箱を整理しよう
さいごに 文化はつくるもの
著者等紹介
山岸俊男[ヤマギシトシオ]
1948年名古屋市生まれ。一橋大学社会学部卒、同大学院社会学修士課程修了後、ワシントン大学社会学博士、北海道大学文学部、ワシントン大学社会学部助教授を経て、北海道大学大学院文学研究科教授、同大学社会科学実験研究センター長。社会心理学専攻(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
京都と医療と人権の本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
りょうみや
12
著者の本は3冊目。前書「信頼の構造」と根本は同じだが、違った角度から集団心理の説明がされている。クラスのいじめ、孔雀のモテ方、終身雇用制度、日本とアメリカの信頼の文化に共通の構造を見出しているところがおもしろい。ゲーム理論や社会心理学のエッセンスが分かりやすいと思える。「心でっかち」「心の道具箱」など本書独自の語句が多く、そこは少し分かりづらかった。2017/04/21
K
5
社会現象や個人の行動の原因を過度に心へと帰属する「心でっかち」(いわゆる心理主義)に対する警告から始まり,システム的な観点から文化差を解釈していくという,人や文化についてのとても興味深い見方を提示してくれる本。 「よく一緒に使う道具同士はセットで手近に置いておく」という「心の道具箱」という考え方も,ユニークでイメージがしやすいと思いました。 本書の原著が刊行されたのはもう10年以上も前ですが,いじめ問題の理解や道徳の教科化についてなど,本書を読んで考えさせられることは多いなと感じます。2013/09/16
ロク=デモス・ナオ
3
盛りだくさん。コスパいいかも。2013/10/14
らっそ
2
気になる一文:実験研究が、質問紙調査や聞き取り調査、あるいは観察研究、個人的な印象などと違う点は、それが結果の曖昧な解釈を許さない点にあります/合理的な判断を下すよりも、ヒューリスティックを用いた方が「正しい」判断になるばあいがある/現在の日本が直面している最大の問題は、これまでの文化的スクリプトのセットが現実の理解に役立たなくなったのに、それに代わるスクリプトを手に入れていない2010/03/17
Yumiko Sato
1
しがらみを科学する、をもう少し専門的に踏み込んだ内容にされた本かと思ったら、こちらの方が先なんですね。「文化の違い」に戸惑うことが多い私にとって、そもそも文化とは何か?を理解させてくれる一冊でした。2013/11/23