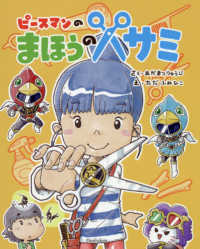内容説明
「一冊の本を読むことは、一人の女と寝ることに似ている―外見だの評判だのは、むろん当てにならない。女は寝てみなければわからない」とは、著者久世光彦の言葉だが、言いえて妙である。稀代の本読みが心を震わせる本と、三島由紀夫、江藤淳、吉行淳之介、保田與重郎、太宰治など思いを寄せる作家に熱く迫る。
目次
女の“片腕”との対話―川端康成「片腕」
いつもの時刻―内田百〓(けん)「サラサーテの盤」
桜色の恋物語―川上弘美「春立つ」
キイ・ワードは“小”―川口松太郎「櫓太鼓」
葉子―大岡昇平「花影」
死への眼差し―清岡卓行「海の瞳」
蛍は三度現れる―織田作之助「蛍」
老いてなお―岡本かの子「老妓抄」
“感傷”の大旗―福永武彦「草の花」
空の花篭―渡辺温「温哀相な姉」〔ほか〕
著者等紹介
久世光彦[クゼテルヒコ]
1935年東京生まれ。東京大学文学部美学科卒業後東京放送を経て、映像製作会社を設立、ドラマの演出を手掛ける。92年「女正月」他の演出により芸術選奨文部大臣賞を受賞。作家活動としては93年『蝶とヒットラー』でBunkamuraドゥマゴ文学賞、94年『一九三四年冬―乱歩』で山本周五郎賞、97年『聖なる春』で芸術選奨文学部門文部大臣賞、98年紫綬褒章など数々の賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
青蓮
101
1冊の本を読むことは、一人の女と寝ることに似ているーー外見だの評判だのは、むろん当てにならない。女は寝てみないとわからないーー久世光彦による、書評、作家論、解説を集めた1冊。読んだことのない作家さんが多数、取り上げられていて、本書を読むと読書の幅が広がりそう。そして久世さんが作品に向ける慈愛に満ちた優しい眼差しを感じます。2017/12/27
メタボン
22
☆☆☆☆ 久世光彦らしい甘美でノスタルジックな書評、作家論。吉行淳之介の特徴として「生勃え(なまおえ)」「熱めく(ほめく)」という言葉をあげるのはまさしくと共感。太宰治論では過去帳(点鬼簿、鬼籍とも言い、ある家計の死者の名を年代順に記したもの。鬼籍に入る)を取り上げ、金木の太宰の生家や菩提寺をすぐさま想起させた。表題作の三島由紀夫論は、その文章自体が硬質なファンタジーと言っても良い。野溝七生子の「眉輪」が気になった。こういう作品を発掘してくるのも久世の真骨頂。2025/01/04
更夜
15
久世光彦さんが亡くなったのは2006年。耽美の世界を私にそっぽを向きながら、目を合わせずにそっと教えてくれる人はいなくなりました。副題に「ぼくの感傷的読書」とあるように本についての本はたくさんあっても、こんなに感傷的で、うしろめたく、そして魅力にあふれた文章で「惚れた作家」「惚れた本」について静かに語り、決しておしつけたりしないその姿勢は私の永遠の憧れです。「論」や「研究」よりも、惚れた作家の小説を何度も読むがいい、と語る久世さんの文章はいつも微熱を持っています。本当に本が好きな人でした。大好きです。2015/09/03
不在証明
14
Ⅰ―解説ではなく書評。一つの作品について、盛り上がりの場面も、オチも、惜し気なく盛り込まれ、少ないページ数で書かれている。限られた字数でこうもうまく纏め上げられるのか、と陶然とする。いくらか読んだ本がある。本当に読んだ本かと一瞬忘れかけるが、やはり読んだと記憶にある。ずれを感じたわけは、物語中のわかりやすい要点ばかりを拾ってはいないからだろう。言ってしまえば、物語の良い面ばかりが目に付く(これは貶しているわけではない)。未読の本も手に取りたくなる、こんな素敵な文章を書く人だとは知らなかった。2016/09/11
tonpie
9
小林秀雄について。「鋭敏な彼の目からすれば、周りはお人好しばかりだった。熱気はあっても盲目的で、文学はそれらの人々にとって信仰ではあったが、その実むなしい幻でしかない。いずれ独走できることは、目に見えていた。(けれど、彼を)笑ったら、半世紀もの間、彼のあの目に、クモの糸のようにからめとられていた自分を笑うことになる」。三島由紀夫について。篠山紀信撮影の「三島由紀夫の家」を傍証に「少女小説に憧れ、それが規範だった人」と見る。人生の半分読書に浸っていた演出家が本を通じて語る、最晩年の感傷的告白。かなり苦い。 2020/05/28