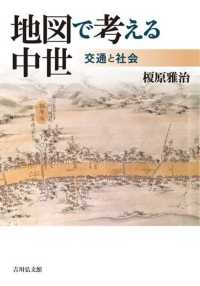出版社内容情報
脱ぎたてのお父さんの靴下の60倍以上くさいという魚の缶詰「シュール・ストレミング」。世界にはなぜこんな食べものが存在するのか? その謎に迫る。
内容説明
納豆なんてかわいいもの。世界にはにおいを嗅いだだけで気絶しそうなくさい食べものがたくさんある。あるどころか多くの人が喜んで食べている。いったいなぜ?!それは栄養があって、なんといっても美味しいから!一緒にくさい食べものの奥深い世界を旅しよう!
目次
第1章 魚類
第2章 調味料
第3章 肉類
第4章 大豆製品
第5章 野菜類
第6章 チーズ類
第7章 漬物類
著者等紹介
小泉武夫[コイズミタケオ]
1943年、福島県の酒造家に生まれる。東京農業大学名誉教授。農学博士。専門は食文化論、発酵学、醸造学。現在、日本各地の大学の客員教授や、発酵食品ソムリエ講座・発酵の学校校長、特定非営利活動法人発酵文化推進機構理事長などを務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アキ
110
世界一くさい食べもの なんと言ってもくさい食べものの王様は、スウェーデンの魚の缶詰「シュール・ストレミング」です。ニシンを開いて塩を少々加え、乳酸菌を主とした微生物で発酵させ、加熱殺菌せずに缶詰にする。炭酸ガスが充満しているので、開ける時に注意が必要です。その1決して家の中では開けない。その2雨合羽などで全身をおおう。その3缶詰を冷蔵庫で落ち着かせる。その4風下に人がいないことを確認する。それだけの苦労をしてでも食べるのは、発酵食品が制約のある中必要に迫られて生み出された人々の知恵の結晶だからなのですね。2022/01/23
けんとまん1007
63
やっぱり、小泉先生は楽しい。それも、単に楽しいだけでなくて、奥が深い。くさい・・・匂いが強烈過ぎるので、くさいという表現になるのだと思う。匂いと香りの違いは、何だろうと考えたことがある。それにしても、人間というものの凄さを感じる。そんな、とんでもないくさい食べ物を作るということもあるが、それが、食べられる文化があり、今日も残っているとということだ。慣れというのか、麻痺というのか、まあいずれにしろ、食べて美味しいから残るのだと思う。最後のほうにある、日本のキムチモドキの話は、考えさせられる。2023/02/20
よこたん
48
“腐敗したタマネギに、くさやの漬け汁を加え、それにブルーチーズとフナ鮓、古くなったダイコンの糠漬け、さらには道端に落ちて靴で踏まれたギンナンを混ぜ合わせたような空前絶後の凄絶なにおいであった。” 発酵食品、くさい食べ物大好き小泉先生ですら、衝撃を受けたシュール・ストレミング。ニシンの発酵缶詰。好奇心で突っ走って大惨事案件。普通に生活している範囲では、遭遇する心配はなさそう。世界にはくさい食べ物が沢山あると知る。なれてもくさいものはくさいと思うんだけど…。くさいキビヤックをチューっと吸うイラストはかわいい。2022/01/09
亜希
25
図書館でふと目に止まって借りてみた。この中で実際嗅いだことのあるのは大島で出会ったくさやぐらいだけれど、あれは確かにめちゃくちゃ臭かった。シュール・ストレミングは昔ダウンタウンの番組でやっていたような…。なんて前半はふむふむと読み進めていたけれど、"肉類"の章には吐き気を覚えました。ヒツジの血の腸詰めや、アザラシのお腹の中に水鳥を羽もむしらず入れて発酵させ、羽を抜いて肛門から体液を吸い出すとか…おえぇ。最初は写真も載っていたら良かったなぁなんて思っていたけれど、この可愛いイラストで十分ですわ。2022/11/29
鯖
17
ニラが星よっつなのはホントか…。あざらしの腹に100羽の水鳥詰め込んで2年以上埋めて発酵させるキビヤックとシュールストレミング(星5つ以上)とその他の間に越えられない壁があるのを感じた。2022/01/14
-
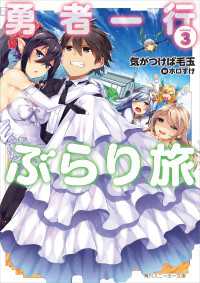
- 電子書籍
- 勇者一行ぶらり旅3 角川スニーカー文庫
-
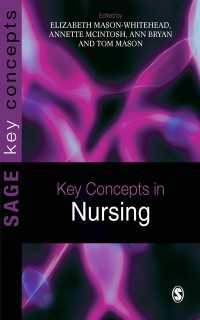
- 洋書電子書籍
- Key Concepts in Nur…