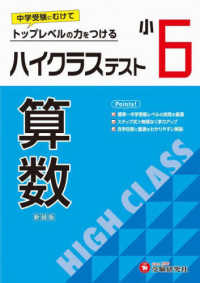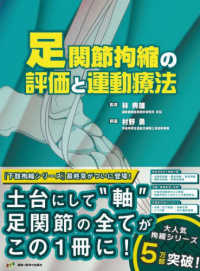出版社内容情報
なぜ大人は本を読めというのだろう? 頭と目を鍛えるための本の読み方を伝授しよう。問題の解決に力を発揮する最強の武器に自分がなる!
内容説明
本を読むと、頭の中に知識のネットワークができるし、広い視野で世界を見る目がもてるようになる。解決したい問題やもっと理解を深めたい物事に出会ったとき、その頭や目が威力を発揮する。進みたい道へ自由に歩き出せるようになる。そのための本の読み方を全力紹介。
目次
第1章 読書の効用(クモの巣電流流し;道具としての知識;「勉強の仕方がわかったぞ」(?) ほか)
第2章 読書の方法(「投網漁法」から「一本釣り漁法」へ;読書会をやってみよう;図書の先生を大いに活用する ほか)
第3章 レジュメ(読書ノート)の作り方(1冊まるまるレジュメを作る;レジュメは本を読み終えてから作る;電子書籍や電子ペーパーを活用する)
次に読んでほしい本
著者等紹介
苫野一徳[トマノイットク]
1980年生まれ。兵庫県出身。哲学者・教育学者。熊本大学教育学部准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
-





Hr本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アキ
102
ちくまQブックス2冊目。「読書は僕たちをグーグルマップにする」とにかく大量の読書経験を積めば、ある時突然、自分がグーグルマップになって、入り組んだ迷路の全体像が見えてくる。いい表現だな。1冊の本の構造を捉えること。本には問いと方法と答えが存在しており、それを意識して読めばその構造的思考をいつしか取り入れることができる。第2章で読書の方法もさまざま紹介しており、参考にしたい。第3章:本を読み終えたら、本の骨格が見えるようにレジュメ(読書ノート)の作り、メモリに保存する。いつかグーグルマップになれたらいいな。2021/12/24
ムーミン
39
レジュメづくり、私のまとめ方と異なる部分もあり、これからの参考になりました。2022/07/20
Speyside
34
哲学者苫野一徳さんによる、中高生向け読書のススメ。とても丁寧に、なぜ読書すべきなのか語っている。速読は不要。丹念にかつ大量に読書をすることで、蜘蛛の巣のごとく教養を身に着け、人生の難題を解決することができる。読書を通じ自分の中に言葉をためれば、意見の異なる他者との間に共通了解を見出し、より良い社会を構築することができる。信念補強型ではなく信念検証型の読書を心がけると同時に、解釈は自分の欲望や関心に寄ってしまうことを自覚し、そのことを表明する。「他者と理解し合うための読書」というのが、建設的でとても素敵だ。2021/09/19
フム
33
ちくま書房が出した10代向けの新シリーズということで図書館から借りてきた。若い人向けとは言っても、この手の新書にはよい内容のものが多くて勉強になる。私も10代に戻れたら、この本に書かれているように貪欲に本を読んでみたい。とはいえ、まだ遅くはないはずである。「教養の蜘蛛の巣」を少しでも張り巡らせれるようにしてみたい。著者の師である哲学者、竹田青嗣が70歳にして、「一徳、私はやっと勉強の仕方がわかったんだよ。」と語ったエピソードに勇気つけられた。レジュメ(読書ノート)の作り方なども参考にしたい。2022/02/18
shiho♪
31
読書の効用は、頭の中に知識のネットワークができること。それを得るためには「投網漁法」のように幅広いジャンルの新書をたくさん読む必要がある。知識が増えると次は特定の分野の本を片っ端から読みたいと思うようになる。これが『一本釣り漁法』である。 最近はYA向けの新書がよく出ていますよね。今年はこういう本も読み漁っていろんな知識を得たい。『投網漁法』を解禁しよう。2023/01/08
-
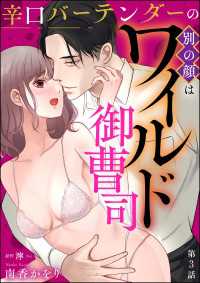
- 電子書籍
- 辛口バーテンダーの別の顔はワイルド御曹…
-
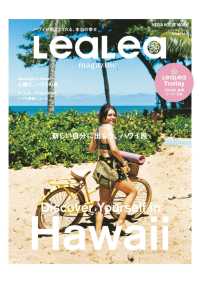
- 電子書籍
- LeaLea magazine SPR…