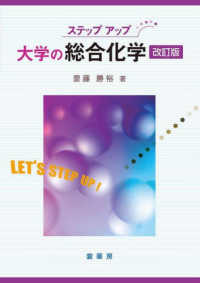出版社内容情報
言葉が意味をもつにはどういう条件が必要か? この難題に現代哲学の第一人者が挑み、切れ味抜群の議論で哲学的に思考することの楽しみへと誘う。
飯田 隆[イイダ タカシ]
内容説明
言葉はそもそも意味をもちうるのか?言語を通したコミュニケーションを可能にする「規則」に、私たちは従うことができるのだろうか?クリプキはウィトゲンシュタインのなかに、こうした問いに否と答える驚くべき議論を見出した。それによれば、私たちが自明のものとして使用する「プラス」のような記号でさえ、「68+57=5」という奇妙な結果に導く可能性を否定することはできないのだ。言語に内在するこうしたパラドックスをいかに解決することができるのか。日本を代表する言語哲学者が切れ味抜群の議論で謎に挑む。哲学的思考への最強の入門書。
目次
第1章 グルー
第2章 クワス算
第3章 懐疑的解決
第4章 ウィトゲンシュタイン
第5章 規則のパラドックス
第6章 論理と規則
著者等紹介
飯田隆[イイダタカシ]
1948年北海道生まれ。主に言語と論理にかかわる問題を扱ってきた哲学者。熊本大学、千葉大学、慶應義塾大学で教え、現在日本大学文理学部教授。慶應義塾大学名誉教授。科学基礎論学会理事長と日本哲学会会長を務めた(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
本屋のカガヤの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
へくとぱすかる
62
プラスではなくてクワス? 57以上のたし算の答えはすべて5? そんなバカな、という反論が通用しない不思議! 言葉の意味についての私たちの信念が、「今までそうだったから、次もそうだろう」という、帰納的推論に支えられていた弱点を突かれたことになる。これが規則・ルールに適用されると、さらに困ったことになるわけだ。後半、推論を正当化するための推論のルールは不要で、無限後退に陥るというウィトゲンシュタインの指摘はズバリわかりやすい。この問題にかかわる議論をもっと読むべきだと思った。次はクリプキの本を読みたい。2020/05/12
月をみるもの
18
演繹は無限後退(=フレーム問題)、帰納はただの経験則(深層学習は内挿はできるだけ外挿は無理)と言われると、なるほど AI が直面してる問題は人間の知性の問題と一緒やんって気づく。「規則に従うことも、それに反することもできない」とか言われたら、海賊匋冥は人工知能(カーリー・ドゥルガー)で、この宇宙を破壊しちゃいそう。。2023/06/24
フリウリ
12
『ウィトゲンシュタインのパラドックス』を読み、クリプキの思考もさらに理解したいと読む。が、クリプキ/ウィトゲンシュタインが述べていた「規則のパラドックス」(規則に対してはどんな振る舞いも、一致させることも矛盾させることもできる)に加えて、「規則のパラドックス」その2(規則に従うことが規則を参照することを含むなら、規則を個別に適用できない)が登場。また、論理的真理は言語的取り決めに従わないという考え方(反・規約主義/言語規則説)は、『思考と論理』における大森荘蔵と反対の立場。ちくま学芸文庫のヌマ…。72025/10/23
てつや
10
シルバーウィーク読書第三弾☆いや、難しかったです。正直途中から目が泳いでしまいました。とくに第三章からはチンプンカンプン。 撃沈です。でも、最初の二章だけでも、とっても面白かったです☆2016/09/19
foo
5
哲学者クリプキの『ウィトゲンシュタインのパラドックス』における仕事を解説した一冊。哲学を学んでいない人にも非常にわかりやすく書かれており、難なく読み進められた。5章と6章だけは理解に骨が折れた(というよりあまり理解できなかった)が、あとがきに「1〜4章は大学1年生向けの講義の再構成、5,6章は哲学を学んだ人に向けた内容」とあり納得した。日頃何気なく行なっている"言葉で何かを意味する"という行為について新しい考えをもたらしてくれる良書。2020/07/04
-

- 電子書籍
- 婚約破棄23回の冷血貴公子は田舎のポン…