出版社内容情報
人はなぜ、どうやって世界を認識し、言語を使い、恋や友情を育み、宗教や芸術など精神活動をするのか? 進化心理学の立場から、心の謎の極地に迫る!
内容説明
人間は友情をはぐくみ、恋に落ち、家族を愛し、笑い、喧嘩をし、人をだまし、幽霊やUFOを信じる。芸術や宗教といった高尚な精神活動に励むと思えば、男は際限なく新たな相手を求め、女は強い男を求める。このとき、人間の心は、そして脳はいったい何をしているのか?上巻で科学的アプローチから解明した人間の精神活動の不思議を、下巻では歴史的、文化的視点を加えてさらに究明する。はたして心が生まれ、このように進化してきた究極の目的とは?心はじつはわれわれ人類が自らのコピーを最大化するために「設計」されたツールなのか!?気鋭の心理学者、ピンカーがついに謎の極限に踏み込む。
目次
第5章 推論―人は世界をどのように理解するか(生態学的知能;カテゴリー化 ほか)
第6章 情動―遺伝子の複製を増やすために(普遍的な情熱;感じる機械 ほか)
第7章 家族の価値―人間関係の生得的動機(親類縁者;親と子 ほか)
第8章 人生の意味―非適応的な副産物(芸術とエンタテインメント;何がそんなにおかしいのか? ほか)
著者等紹介
ピンカー,スティーブン[ピンカー,スティーブン] [Pinker,Steven]
1954年生まれ。スタンフォード大学、マサチューセッツ工科大学で教鞭をとり、現在はハーバード大学心理学研究室教授。著書『心の仕組み』で「ロサンゼルス・タイムズ」ブック賞、「ニューヨーク・タイムズ」ブック・オブ・ザ・イヤーをはじめ、数々の賞を受賞
山下篤子[ヤマシタアツコ]
北海道大学歯学部卒業。翻訳家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
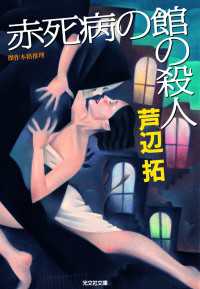
- 電子書籍
- 赤死病の館の殺人 光文社文庫
-
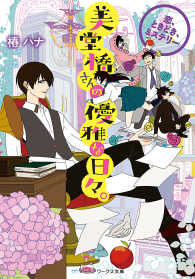
- 電子書籍
- 美堂橋さんの優雅な日々。 - 恋、とき…






