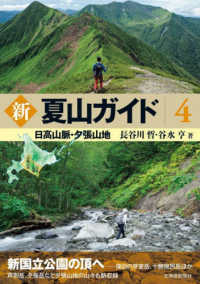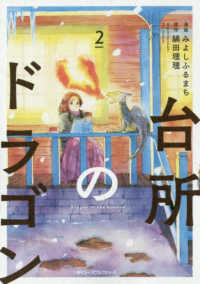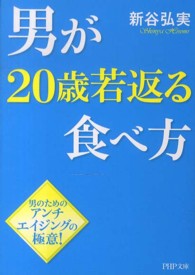出版社内容情報
考古学・古代史の重鎮が、「土地」「年代」「人」の基本概念を徹底的に再検証。「古代史」をめぐる諸問題の見取り図がわかる名著。
内容説明
考古学的な知見と、『日本書紀』『古事記』などの文献資料を織り合わせてはじめて、古代の真の姿が浮かび上がる。この考えから「古代学」を提唱する学界の重鎮が、古代の読み解き方を根本から問い直し、「土地」「年代」「人」の見方をめぐって、具体的かつ革新的な方策を提案する。「土地」の見方では変貌する河内と摂津から国生み神話の鍵などを考察。「年代」の見方では銅鏡の「年代」や「暦」を通して、古代人が時間をどう記述したかを探る。「人」の見方では、倭人=「呉の太伯」の後裔伝承の重要性などを提議。未解明の謎の数々や、古の人びとの心に想いを馳せながら、古代史を総ざらいで生きる入門書。
目次
第1章 土地の見方(海道と島々を考える;変貌する河内と摂津―国生み神話の鍵)
第2章 年代の見方(時間をどう記述したか;銅鏡の「年代」をめぐって;諸所に刻まれた年号;「暦」はどのように使われたか)
第3章 「人」の見方(『古事記』の構造;倭人=「呉の太伯」の後裔伝承の重要性;複数の「倭人」の存在;南九州を考える;海を渡る倭人たち)
おわりに―百済・武寧王の子孫としての桓武天皇
著者等紹介
森浩一[モリコウイチ]
1928年生まれ。同志社大学名誉教授。日本考古学・日本文化史学専攻(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
月をみるもの
11
森さんの晩年の著書は、どれも鬼気迫るものを感じさせる。すべての章において、掲げられた課題は興味深く、そして重い。 たとば以下の記述の切れ味 → "どうやら多くの考古学者や古代史家も、大きな前方後円墳を造営したり多くの銅鏡を保持している者の力を大勢力と誤解している節がある。その二点は人間生活に役立つ着実な生産から考えるとどちらも無駄なことにおもえるが、どうだろう。"2019/07/18
fseigojp
10
ここに述べられた課題は、まだ解決されてないのが多い2024/09/30
浅香山三郎
8
刀剣・鏡・墓碑など出土したものや、伝世したものに刻まれた文字と、記紀や中国の歴史書からの情報を突き合はせて日本の古代の実像を探る。そこには、文献史学だけではなくて、民俗学・民族誌のやうな分野の成果も生かされ、森さんの知識の幅と思考の深さを感じることが出来る。「古代学」を提唱する森さんだが、その学問の面白さは該博な知識の裏付けがあつてこそだということを実感させられる。2023/08/30
くまきん
1
「考古学・古代史課題ノート」という副題がついており、「入門書」である前提でページ数はそれ程厚くないが、かなりレベルは高い。「土地の見方」「年代の見方」「人の見方」の三章から成っており、基本的に先入観や思い込みを排斥する見方を示しておられる。「読者のなかに、もし自説なるものをお持ちの場合も、一度それを横において淡々とおさらいをしてほしい。そのような機会は、誰にとっても一生にそう何度もあるわけではなかろう。」と言うあとがきのことばが印象的だ。この本も後々何回も読み直さなければ…。2015/05/04
kwmr_
0
入門書という位置づけで書かれているが、全くの予備知識なしで読むにはちと辛い。考古学を学ぼうとする学生には良いかも。どんな定説も自らの疑いの目で見ようとする姿勢に脱帽。2011/10/13
-

- 和書
- 土質力学の基礎