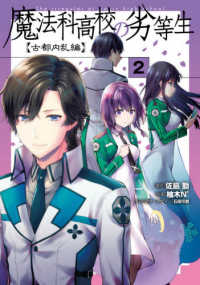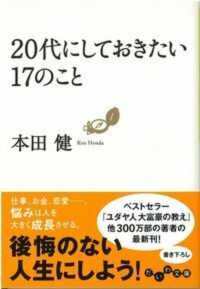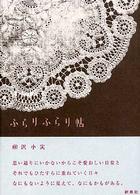出版社内容情報
殷周、縄文、ケルト、メキシコ。西欧的価値観を突き抜け広がり深まるその視線。時空を超えた眼差しの先の世界美術史構想を明らかに。
内容説明
西欧的価値観を突き抜け、日本の伝統を踏み越えて、岡本太郎のまなざしはさらに拡がり、深まっていく。古代からの遺産に生命の絶対感を見、現代人の心の深奥にこの初源的な感動を求める。中国・殷周の青銅器、日本の縄文、ヨーロッパのケルト、ユーラシアの騎馬遊牧民文化、中南米のプレ・コロンビア文化。美の範疇に入れられてこなかった、時代も地域も違うものから、相互に共鳴する、時空を超えた新しい美の世界が浮かび上がる。本巻は『美の呪力』、泉靖一氏との対談『日本列島文化論』を収録、彼の世界美術史構想を鮮やかに展開した「宇宙を翔ぶ「眼」」が掉尾を飾る。
目次
すさまじい美学について
美の呪力
日本列島文化論―日本人は爆発しなければならない(対話)
遙かなりユーラシア草原
中南米に見る生命の深淵
宇宙を翔ぶ「眼」
岡本太郎年譜
著者等紹介
岡本太郎[オカモトタロウ]
1911‐96年。父は漫画家・岡本一平、母は作家・岡本かの子。29年渡仏、地象芸術、シュルレアリスムの運動に参加。パリ大学で民族学、哲学を学び、バタイユらと活動を共にした。40年に帰国、42年中国戦線に出征。46年に復員後、花田清輝らと「夜の会」を結成し、アヴァンギャルド芸術を推進した。『今日の芸術』『日本の伝統』はベストセラーとなった。70年、大阪万博テーマ館のプロデューサーとして「太陽の塔」を制作。以後、テレビをはじめとするあらゆるメディアを通じて発言と行動をつづけた(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
i-miya
i-miya
i-miya
i-miya
i-miya