出版社内容情報
突き当たった「伝統」の桎梏。そして縄文の美の発見。彼が対決した「日本の伝統」とははたして何だったのか。格闘と創造の軌跡を追う。
内容説明
1974年、ロラン・バルトは前衛的季刊誌『テル・ケル』のメンバーともに毛沢東政権下で文化大革命を推し進める中国を訪れる。北京、上海、南京、洛陽、西安をめぐる行程のすべてを彼は克明に記録し続けた。そこでは、書や料理、色彩や風景、訪問先での見聞が記される一方、エロティシズムや“襞”の欠如に嘆き、政治的な配慮に苛立ちながら、中国に「フランス」を照射しようとする。ついに書かれることのなかった中国版『記号の国』へのノートとして2009年に発表された新草稿、本邦初訳。
著者等紹介
バルト,ロラン[バルト,ロラン][Barthes,Roland]
1915‐80年。記号のシステムとしてのテクスト分析により、それまでの批評言語を刷新し、現代思想にはかりしれない影響を与えたフランスの批評家。社会的神話学から出発し、記号学・テクスト性・モラリティの時代を経て、テクストの快楽の実践へと至った。交通事故により死去
桑田光平[クワダコウヘイ]
東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。パリ第4大学博士課程修了。東京外国語大学大学院総合国際学研究院講師。専門は20世紀フランス文学・美術(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
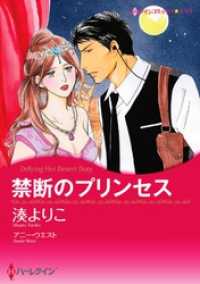
- 電子書籍
- 禁断のプリンセス【分冊】 1巻 ハーレ…
-
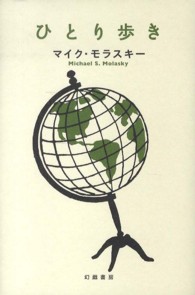
- 和書
- ひとり歩き






