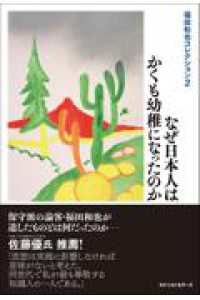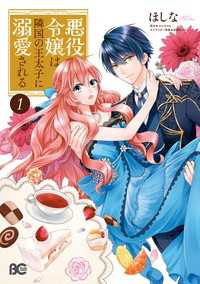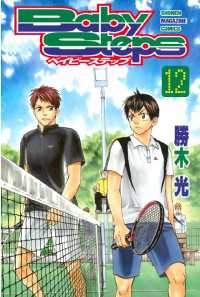内容説明
水銀およびその原料たる辰砂(朱砂、丹砂)は古来、金属精錬、鍍金、医薬、顔料、化粧品などに広く用いられた重要な金属資源である。奈良の大仏が大量の水銀を使って金鍍金されたのはつとに知られている。本書の原型である大著『丹生の研究』は、その水銀を歴史学の対象とする未曾有の試みだった。地名・神社名を史料として用いるという卓抜な発想と徹底的なフィールドワークによって解明される、古代の金属文化、日本ミイラの特異性、採鉱技術者集団とその信仰などは、きわめて示唆に富む。関連の深い論文「即身仏の秘密」、著者の人柄と学風をよく伝える回想「学問と私」を併載。
目次
古代の朱(赤の世界;青丹よし;まがね吹く;丹薬と軽粉;日本のミイラ;水銀の女神;丹生氏の植民;水がね姫の変身;漢字から生まれた神;丹生高野明神;丹生と丹穂;石鏡を考える)
即身仏の秘密
学問と私
著者等紹介
松田壽男[マツダヒサオ]
1903‐82年。東洋史家。文学博士、早稲田大学名誉教授。東京帝国大学文学部東洋史学科卒。第一高等学校講師、国学院大学教授、早稲田大学教授、日本イスラム協会理事長などを歴任した。独自の歴史地理学的方法を駆使した内陸アジア史、東西交渉史研究の第一人者(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
獺祭魚の食客@鯨鯢
42
古代は青、赤、黄、白、黒の五色で方角や季節などを表象した。そのうち硫化水銀に由来する朱色が珍重されたのは「不老不死」「不老長寿」に関係するからである。 平城京など建物の朱色はこれらを塗料としているからだが、それが水銀中毒を引き起こし遷都の遠因になったとも。 不老不死の薬「仙薬」を求めて秦を旅立った徐福は東方の山海「蓬莱山」を目指した。蓬莱山とは「富士山」である。諸説あるが富士山が見える相模には秦野という場所がある。 古代の列島には水銀の産出地が多かったことがその様な伝説が生まれたのだろう。2021/09/25
tyfk
6
「黄金の原鉱石から純金を分離、抽出するには、アマルガム法によるのが、最も容易だからである。これは水銀が金や銀と任意の割合でたやすく合金する性質を利用したもので、合金して飴のようになった金アマルガムに熱を加えて、水銀を蒸発させてしまえば純金がえられ、また金アマルガムを、例えば仏像などの金属製品に塗りつけてのちに、水銀をとばしてしまえば鍍金ができる。」2023/08/13
チューダー
5
古代日本は朱砂の産地であったと聞くが、今日知られている辰砂の毒性とは裏腹にこんなにも重宝されていたのか、と思うと妖しさが一層増す。 全国にある丹生という地名と丹生氏との繋がりも興味深いが、地名や神社、伝承にのみ名残があり産地であったことも忘れられているという。 それらを掘り起こすため、現地に足を運び全国を調べ上げている貴重な文献だと思う。 地図や注釈が手書きなので読みにくくて、実際に読みたくても読めないところがあり残念だった。現在の地図や写真が載っているのもっと楽しめたと思う。2023/04/30
Junko Yamamoto
2
朱まみれの古墳内部から、古代日本人が朱あか、に執着していたとわかる。 歴史を点→線→面と見る視点も面白い。2018/01/08
まる
2
この本の前に読んだ、聖地巡礼continuedとシンクロしまくって驚いた。これまでは辰砂というものを密教的な面からしかみてなかったけど、空海との繋がりなどから金の精製方法まで多面的に知れたことはとても興味深かった。また、この朱砂を追って移住していった丹生氏や壬生氏の痕跡を土地の名などに探す時に、推察する過程がとても勉強になった。それにしても、大昔でさえその時の暮らしの都合や朝廷への忖度などで祀る神が変わっていくのをみると、人間てホントある意味すごいわと呆れる。2017/11/20