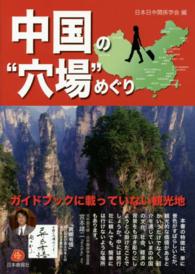内容説明
「これはエクリチュールについての本である。日本を使って、わたしが関心を抱くエクリチュールの問題について書いた。日本はわたしに詩的素材を与えてくれたので、それを用いて、表徴についてのわたしの思想を展開したのである」。天ぷら、庭、歌舞伎の女形からパチンコ、学生運動にいたるまで…遠いガラバーニュの国“日本”のさまざまに感嘆しつつも、それらの常識を“零度”に解体、象徴、関係、認識のためのテキストとして読み解き、表現体(エクリチュール)と表徴(シーニュ)についての独自の哲学をあざやかに展開させる。
目次
かなた
見知らぬ言葉
沈黙の言語
水と破片
箸
中心のない食物
すきま
パチンコ
中心‐都市 空虚の中心
所番地なし〔ほか〕
著者等紹介
バルト,ロラン[バルト,ロラン][Barthes,Roland]
1915‐80年。フランスの思想家、記号学者。シェルブールの軍人の長男として生まれる。カミュの『異邦人』に触発され“エクリチュールの零度”という観念を抱く
宗左近[ソウサコン]
1919年、福岡県生まれ。詩人、仏文学者(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
-





読書という航海の本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
やいっち
72
本書には、表徴の帝国が小生には夢のように繰り広げられていて、不思議な本だった。冒頭の短詩は、榎本其角の俳句(瓜の皮水もくもでに流れけり)のバルトによるフランス語訳を宗 左近氏が日本語に訳したものである。その後に続く地の文は、無論、バルトの文(を宗 左近氏が訳したもの)である。 バルトの文章もこうした素材を扱った文章で読むと、結構、楽しい!:
ころこ
48
本書で思い出すのは、数年前にアレクシェーヴィチが福島に来て語ったとき、「的外れ」と暴言を吐いた連中がいたことです。アレクシェーヴィチやナンシーが自らの問題として何かを言いたいのだから、我々の文脈とは解釈が違って当然です。むしろ、我々と違うことをもって、彼らが世界で起こった何かに対して考えたということを有り難く感じない感性とは何なのかと不思議に思います。本書も日本のことを分析している訳ではありません。かといって、何をいっているのか要領を得ない断片の集積が、彼がみた日本のキッチュさを上手く表現しています。2019/07/15
zirou1984
41
23区の中心に存在する皇居に対し「いかにもこの都市は中心をもっている。だが、その中心は空虚である。」と述べたことで有名な、日本を題材としたバルトによる表徴論。表徴とは裂け目である。しかし、裂け目から覗いているのもまた、神聖なる〈無〉を覆い隠すためのもうひとつの表徴であるーこのような視点から和食や俳句、果てはパチンコや全学連までを論じるバルトの眼差しは時に過度なきらいはあるものの、時にはっとさせられる内容もあり面白く読めた。特に、女方について「内部の男性はただ、不在化されているのである」という指摘は白眉。2016/10/23
A.T
26
巻末の「解説」から読むことをおすすめ。表紙の仏像に騙されて、日本文化論について書かれているのかと早とちりしてしまった。フランス人が日本を肴に「構造主義」を論じてる話なのだった。美術書にもかつてよくコメントがあった「構造主義」って何なのか、いまだに知ろうともしてこなかったけど… どうやら「去年マリエンバートで」やロブ・グリエの小説も構造主義の考えからつくられていたんだという。ああ、それなら好きな世界かも。というわけで、感想は再読した時に。2023/04/04
松本直哉
23
種々の日本の文物を論じた中でも白眉は俳句論ではなかろうか。翻訳という障碍にもかかわらず、著者ならではの切り口で俳句の本質に肉薄しているように思える。桑原武夫の第二芸術論へのアンチテーゼとして読むことはできるだろうか。首尾一貫した主体が明確な個性をもって作品を支配し意味を充溢させるというロマン派的ブルジョア的な桑原の文学観では捉えきれないのが俳句であるが、このような文学観こそバルトが生涯を通じて批判しつづけたものだった。主体から切り離された宙吊りの言葉が、意味に向って開かれる。文学の新たな可能性。2016/06/04
-

- 電子書籍
- 豚公爵に転生したから、今度は君に好きと…