内容説明
不安や死への自覚を介して未来へと先駆しながら、今において覚悟的に生きる本来的実存が示されるとともに、存在論の基礎となるべき時間性が解明される。
目次
第2編 現存在と時間性(現存在の可能的な全体存在と、死へ臨む存在;本来的な存在可能の現存在的な臨証と、覚悟性;現存在の本来的な全体存在可能と、関心の存在論的意味としての時間性;時間性と日常性;時間性と歴史性;時間性と、通俗的時間概念の根源としての内時性)
1 ~ 1件/全1件
- 評価
本屋のカガヤの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
さきん
30
人間が自ら「ある」ことを了解した(現存在)上で、物事に「ある」を見出す(存在性)ところまでが前巻。その上で現存在たらしめる関係は何かということで、時間、とりわけ人間には死(無)が訪れることを指摘。死を前にして現存在として認識して生きていくことを本来的、逃避してまたは気づかないで生きていくことを非本来的とし、非本来的な事例として大衆社会を上げる。良心とか最後に歴史性の話が出てくるが、道徳とか共同体についても話したかったのではないかと思った。死に相対し、そのために生きるというのは正に武士的価値観。2021/10/15
wadaya
14
上巻は大前提として現存在が在ること、つまり存在了解がアプリオリにある地点から論理が成り立っていた。そしてもし、その現存在が無ければ存在という概念が無いだろうと言っている。ハイデガーは上巻の最後に、それは限定的だと述べている箇所がある。僕の持論でもあるが、本当は現存在が実存すること自体が限定的であり、例え現存在が存在しなかったとしても「世界=内=存在」の構図は変わることなく、世界の存在を否定することはできないだろう。実存主義は間違っていない。ただ限定的であるとは思うけど。さて前置はこれくらいにしようか。→2021/07/18
K
10
上巻の現存在分析はそれなりについていけた感があったが、下巻の時間性分析は全然と言っていいほどダメだった。分析哲学の時間論だけでなく、時間経験の哲学にも少々触れてきてはいたが、あまり入ってこなかった。早く自分の解釈を作り上げたいところではある。時間性についても、少しづつ理解していければと思う。2022/08/05
オカピー
9
ハイデッガーの著書は、名前は知っているが読んだことがありませんでした。「存在と時間」という題名で、身近にある言葉(単語)であり、親近感がある著書かなと少し期待していましたが流石に難解。「物」が目の前にあることが「存在」していることの証ですが(認識できるもの)、物だけでなく考え方や認識できない現象も、存在という概念の中には入るのかな。もう一つ「時間」は、時計というもので時間が経過していくのがわかるが、時計が無くてもやはり「時間」は「存在」し、経過していく。とか、色々考えながら読んでいると1カ月かかりました。2023/11/22
みき
8
存在の切れ目なさや、現時点でそこにいるがそこにいることだけではない包括さ、とか、存在を構成する要素をひとつひとつ「思い詰める」ような解釈を与えている。存在に関する説明の至らなさは、その「まだ足りない」というところに存在の裏付けがあるのかなー。量子力学論のような、どんな状態でも存在しえる、とういことが存在することの裏付けなら、このアプローチの結果はどこに行けるか、わからないなと思った。面白かった。2017/12/09
-

- 電子書籍
- ゾンビ姫に抱っこ!【タテスク】 #06…
-
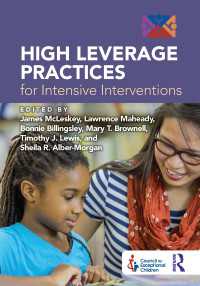
- 洋書電子書籍
- High Leverage Pract…






