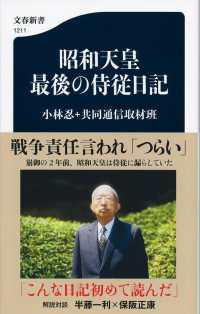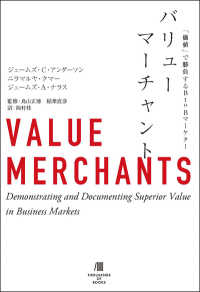内容説明
創造的なエネルギーが爆発した江戸時代、民衆の力は既成の宗教を軽々と離脱し、時代を反映する小さな神々を生み出す。お地蔵様、お稲荷さん、七福神、お札参り、エエジャナイカ、霊験…。うわさ話がいつしか熱狂的な信仰の対象となったこれらの神は〈はやり神〉と呼ばれる。民俗史料やいまも残る流行神を渉猟し、さまざまな事例から江戸から今日にいたる時代性と民俗の相関を考察する。流行神信仰の背後にある民衆の心理や宗教意識、日本人の精神構造の基底を丹念に掘り起した力作。
目次
1 流行神の諸相
2 流行神の系譜
3 流行神仏の性格
4 流行神の思想
5 流行神の構造
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
恋愛爆弾
25
宮田登の注目するところに「終わり」はいつもつきまとうが、それは本書において「中断」という形式をとる。流行るものがいずれ廃れるとして、それは政治的怨霊が和霊へと、あるいは疱神が福神へと、人びとのなかで認識のポジティブで有用な変化をたどるなかで、想像力の有限性は村落共同体における秩序を支えるものでしかない。だが、われわれはそれでも一度は自ら「中断」することが可能であると本書は証明する。それに嫌気がさしたわれわれが、たとえ幾度もネガティブで無用な変化を辿ろうと、その有限性だけは手放してはならないのだ。2023/06/01
ワッピー
22
諸星作品:紙魚子の「祀り捨て」という言葉から。江戸から近世にかけて一時的に参拝客を集めるも、すぐ忘れられ、廃れていく「はやり神」について考察。神の系譜や由緒、また信仰する側の祈りの種類についても触れ、どのような社会情勢の中で「はやり神」現象が起こりやすいのかを検証し、社会不安、終末観の中で「世直し」的な意味を無意識的に発散する民衆のオルギーとリンクしていることを明らかにする。様々な宗教現象から現代の都市伝説までを網羅した社会心理学的名著。巻末の江戸時代からの社会的事象と宗教的事歴の対比表は非常に興味深い。2022/03/29
Toska
6
農村の神頼みが多く共同体単位で行われる(雨乞いなど)に対し、個人化した社会では祈願の内容も人様々で、それ故に多種多様な流行神はどちらかと言うと都市的な現象であるとのこと。成程。流行神は必然的に「廃れる」プロセスも伴うわけで、幕末のエエジャナイカのように一時的な爆発的流行はあっても、社会を動かす新たな宗教運動として定着することはなかった。この辺りは、大規模な宗教反乱が王朝を転覆させるケースさえあった中国などと比較するとどうだろうか。2022/02/17
たねうま
4
まるで、漫画やアニメのキャラクター、アイドルのように、昔の神々も消費されたのだなぁ。縁起のいい神様は、空から降ってくるか、海から流れてくるか、地中から掘り出されるかしかないという仮説は、どこぞのロボットアニメやラブコメと重なっていて苦笑した2012/10/02
さんとのれ
2
共同祈願から個人祈願へと変わり、多様化する民衆の欲求に応えて現れる数々のハヤリ神。そのいくつかはリーダーを得て組織化され、共有される価値観を得て宗教として定着していくわけだけど、一時的な風俗として祀り棄てられ忘れられていくその他のハヤリ神とどこが違うのか、そのあたりについての言及は残念ながらなし。2013/11/01