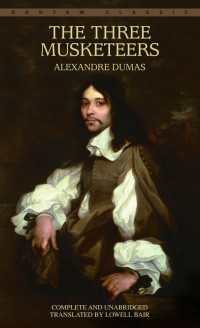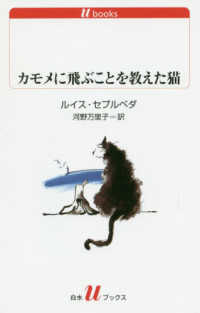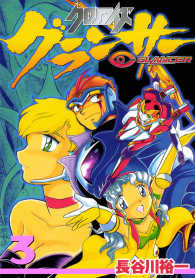出版社内容情報
古代の漢字受容から、近現代の漢字簡素化まで、日本における漢字の歴史を日本の文化や人々との係わりを通して描き出す。深い漢字文化理解のための必携の通史。
内容説明
中国で生まれた漢字は日本語と邂逅し、日本文化に大きな影響を及ぼした。字形・字音・字義は日本独自に発達した面も少なくない。本書は日本における漢字の歴史を言語の側面のみならず、日本の文化や人々との係わりを通して描き出す。古代における漢字の受容、漢文・漢語の定着と万葉仮名の展開、中世の漢字・漢文の和化、和漢混淆文と字音の独自変化、江戸時代の漢学・漢字文化の隆盛、そして近代以降の漢字簡素化・字形整理―より深い日本の漢字文化理解のための必携の通史。
目次
第1章 伝来―五世紀まで
第2章 受容―六~八世紀
第3章 定着―九~十二世紀
第4章 伸長―十三~十六世紀
第5章 流通―十七~十九世紀中頃
第6章 発展―十九世紀中頃以降
著者等紹介
沖森卓也[オキモリタクヤ]
1952年生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科修士課程修了。立教大学名誉教授。博士(文学)。専門は日本語学。とくに日本語の歴史的研究。『辞林』シリーズ(三省堂)を長く監修、執筆してきている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
よっち
26
中国で生まれて日本語と邂逅し、日本文化に大きな影響を及ぼした漢字。日本の漢字文化史をより深く理解するために書かれた1冊。日本にいつ漢字が伝来したのか。古代における漢字の受容、漢文・漢語の定着と万葉仮名の展開、中世の漢字・漢文の和化、和漢混淆文と字音の独自変化、江戸時代の漢学・漢字文化の隆盛、そして近代以降に進められた漢字の簡素化と字形整理の歴史が紹介されていて、言語体系の異なる中国の影響を受けながらも、それを独自の形に発達させていった日本の漢字文化の歴史の要点を通史としてざっと学べる一冊になっていました。2024/12/04
Nobu A
21
沖森卓也著書初読。昨晩から温泉施設に投宿し、2025年新年早々の読了。手に取った理由は漢検1級の勉強に役に立たないかなと淡い期待から。正直見事に、いやそれは言い過ぎか、でもかなり裏切られた。タイトルは漢字全史と銘打っているが、どちらかと言うと「漢字関係者とその書籍全史」宛ら。漢字が中国や韓国からどのように受容され、変化していったかより周縁情報、人名や書籍名が夥多しい。最終章でワープロ及びネット普及後の常用漢字表等に触れているが、漢字そのものの習熟度向上の手助けにはならない。残念無念。後半流し読み読了。2025/01/01
さとうしん
18
漢字伝来からJIS漢字まで、漢字の字形、字音、(特に日本での)字義、漢語、漢文等の文体、訓読、部首、仮名、印刷、辞書等々の変化や展開をたどる。通常あまり詳しく触れられない唐音や唐話についても詳しい。教科書・便覧的な使い方もできそう。近現代、特に戦後の状況が駆け足気味なのは少々残念だが、それでも要点はちゃんと押さえてある。2024/11/14
bapaksejahtera
16
日本語に語彙音韻は勿論、我らの美意識や思考に決定的な影響を与えた漢語の活用の歴史を、歴史時代以降現在迄幅広く論じた、新書であるが大部な本。言語や文字に留まらず文学芸術史の記述も長く、やや焦点がずれる印象もあるが、さりとてどこ迄の範囲が妥当か判断がつかぬ。異国の文字が、全く系統を異にする言語に持ち込まれ、訓読という独特な利用が図られる。漢地と程よく離れ都合よく利用できる環境、漢語が母国の変異多様な方言間の便利なツールとして活用される物であった点も有利だった。名乗りの成立、反切による占い等興味深い記述が満載。2025/01/21
アメヲトコ
9
2024年11月刊。日本への漢字伝来から今年の改正戸籍法まで、日本における漢字史を網羅した一冊です。一番複雑怪奇なのは中世の字音変化で、我々が何となく使い分けている読み方も理屈を考えると相当に複雑で、これは外国人泣かせだろうなとも。定価1320円と新書にしては高めですが、相当に目配りのきいた内容で、情報量からするとむしろ安い。まだまだ勉強が足りないことを自覚させられる一冊でした。2024/12/11