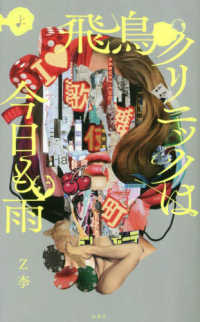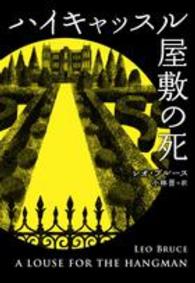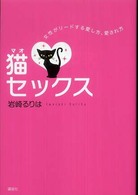出版社内容情報
「お」の付く女性名はどこに消えたのか? 江戸時代の女性名が、明治期に男女共通の「氏名」となり、現代の諸問題を抱えるまで。人名の歴史的変遷を明らかにする
内容説明
江戸時代の女性名は現代とどう違ったのか?「お」の付く女性名はどこに消えたのか?近代女性名の「子」とは何か?何が今日の「夫婦別姓」論争を生み出したのか?アイデンティティとして名前に執着する現代の常識は、どのように生まれたのか?―男性名とは別物だった江戸時代の女性名が、明治期に男女共通の「氏名」となって現代の諸問題を抱えるまで、近代国民国家の形成、文字の読み書きや捺印、戦後改革など様々な事象を通して、日本人名文化の歴史的変遷を明らかにする。
目次
プロローグ―愛着の始まりを探して
第1章 江戸時代の女性名
第2章 識字と文字の迷宮
第3章 名付け・改名・通り名
第4章 人名の構造と修飾
第5章 明治の「氏」をどう扱うか?
第6章 「お」と「子」の盛衰
第7章 字形への執着
第8章 氏名の現代史
エピローグ―去る者は日に以て疎く…
著者等紹介
尾脇秀和[オワキヒデカズ]
1983年京都府生まれ。佛教大学大学院文学研究科博士後期課程修了、博士(文学)。現在、神戸大学経済経営研究所研究員、花園大学・佛教大学非常勤講師。専門は日本近世史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
139
夫婦別姓反対論者は「家族の一体感を壊す」と主張するが、明治になるまで嫁は実家の姓を名乗っていた。江戸時代に女性の識字率は男に比べ低く、この字はこう書くという規定すらなかったので多表記表現が普通だった。女の名に「子」を付けるのは貴族階級の流行からで、それまでは存在しなかった。女の氏名にまつわる様々な常識が打破されていき、従来のこだわりや思い込みが苗字強制令と戸籍制度整備以降のものだと思い知る。制度のない時代は自由にしていたが、制度に従うのに慣れるとそれ以外は考えられなくなる。人の無知といい加減さを証明する。2024/12/07
ネギっ子gen
59
【「お」の付く女性名はどこに消えたのか。何が現在の「夫婦別姓」論争を生み出したのか――】本書は女性名を主題にして、明治期に男女共通となった「氏名」が、現在までの間にどのような社会的な変化により新たな執着・愛着を形成したのかを明らかにするものである。巻末に参考文献。<日本の人名に時代を超えた“正しい形” “正しい文化”なぞ存在しない。自分が抱いている氏名へのこだわりとは何なのか――。本書をきっかけに少し疑問を持ってみつめてほしい。すると現在の氏名をめぐる問題に、何か違った見方もできるのではないか>と。⇒2025/01/04
よっち
39
男性名とは別物だった江戸時代の女性名が、明治期に男女共通の「氏名」となって現代の諸問題を抱えるまで、日本人名文化の歴史的変遷を明らかにする1冊。「お」の付く女性名はどこに消えたのか?近代女性名の「子」とは何か?識字の問題とかな文字、仮名遣い、似て非なる捺印文化から、名付けと幼少期や婚姻時、法名への改名、奉公と通り名、朝廷女官のそれぞれの呼名。男の人名構造と女性名の変遷、苗字や妻の呼び方。近代氏名の時代への移行、「子」の字の流行と変質に見る「お」と「子」の盛衰から氏名の現代史までなかなか興味深く読みました。2024/10/06
niisun
35
これはなかなか興味深く読めました。昨今の夫婦別姓の議論を行う上で一読の書かと。古来より明治まで、男と女では名前の作り(構成)も意味や位置づけも全く違った。男子の名は個人を識別する“名”、一族やグループを称する“氏”、役割を表す“姓”、そこに官位・位階、通称、称号、苗字、屋号などが時代時代のルールで組み合わさって成り立っていた。“名”こそ変わらないが、現代の“氏”はかつての“氏”とは意味が異なる。また、女性には明治期よりも前まで“名”しかなかったし、民法制定まで女性の姓は結婚後も実家の姓を用いる規定だった。2024/10/28
さとうしん
23
『氏名の誕生』の姉妹編で、前著で描ききれなかった女性の氏名について。「お」のつく名前と近代の「~子」との関係、表記の揺れ社会的身分の変化に伴う改名、苗字をつけないものとされていた女性の名前、そして近代以後の氏名政策と氏名の混乱のはじまりといった話題を扱う。しかし実際のところ、本書は女性の氏名にとどまらず、男性の氏名も含めた印鑑の問題、近代以後の漢字表記の問題、姓名判断の流行など、幅広い内容を扱っている。漢字表記の問題に関心のある向きも読んで損はないだろう。2024/09/28
-

- 和書
- 災厄 角川文庫