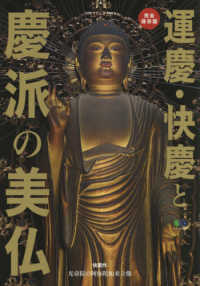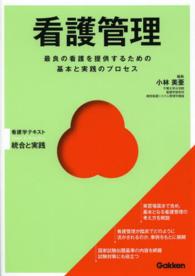出版社内容情報
日本の農村に息づくさまざまな知恵は、現代社会に多くのヒントを与えてくれる。社会学の視点からそのありようを分析し、村の伝統を未来に活かす途を提示する。
日本の村々は、長い歴史のなかで工夫に工夫を重ね、それぞれの風土に根ざした独自の生活パターンと人づきあいのあり方をかたちづくってきた。そのしくみや特徴をつぶさに観察してみると、村を閉鎖的で前近代的なものとみなすステレオタイプこそ、むしろ古びたものにみえてくる。コミュニティの危機が叫ばれる今日、その伝統を見つめなおすことは私たちに多くの示唆を与えてくれるのだ。日本の村に息づくさまざまな工夫をたどり、そのコミュニティの知恵を未来に活かす必読書。
内容説明
日本の村々は、長い歴史のなかで工夫に工夫を重ね、それぞれの風土に根ざした独自の生活パターンと人づきあいのあり方をかたちづくってきた。そのしくみや特徴をつぶさに観察してみると、村を閉鎖的で前近代的なものとみなすステレオタイプこそ、むしろ古びたものにみえてくる。コミュニティの危機が叫ばれる今日、その伝統を見つめなおすことは私たちに多くの示唆を与えてくれるのだ。日本の村に息づくさまざまな工夫をたどり、そのコミュニティの知恵を未来に活かす必読書。
目次
第1章 村の知恵とコミュニティ
第2章 村とローカル・ルール
第3章 村のしくみ
第4章 村のはたらき
第5章 村における人間関係
第6章 村の評価と村の思想
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
tamami
50
本書が対象とする村は、江戸時代以来の村、現在で言う自治会あるいは地域コミュニティに近い。副題に「日本の伝統的な人づきあいに学ぶ」とあるように、村の中で育まれてきた、自然とも仲良くし「つとめ」の気持ちで仲間とつきあい、共に生きていくという生き方の智慧について記す。村社会におけるタテとヨコの人間関係、あいさつの型、様々な「講」の意味や寄り合いの働きなど、普段は何気ない行動の形としてしか意識することがなかった事柄の持つ「裏」の意味も教えられる。「近代」が問い直されようとしている今、古きを温ねる意義も少なくない。2023/04/11
ぷほは
12
学会会長職としての仕事の片手間ではあるだろうが、エッセイとして質が高く、さらりと書かれている情報の奥行きと広がりが素晴らしい。行間を読む訓練として学生に勧めたいと同時に、新自由主義者をおとぎ話の「猿」に見立てる語り口がいちいち社会学者らしくて感動する。こうした好々爺的な書き手による柔らかい豊穣な文体を拝める機会も徐々に減ってきているように思う。それは私のライフステージの問題なのか、業界の問題なのかは微妙なところだが、おそらく両方なのだろう。それよりさらに遠い今の学生たちに、この感覚を遺しておいてあげたい。2023/05/07
sakanarui2
7
家族の本棚でみつけた本。 地域活動をする中で、農村の集落にルーツがある自治会と、新規住民との話の噛み合わなさに困ってたので、大いに役立ちそうな情報満載でありがたかった。 村のポジティブな側面や、村を守りたい人々の心理、保守の思想の片鱗に触れ、自分がいまま間違ったアプローチばかりをしてたことにも気付くことができた。 とはいえ、慣れない村の掟には拒否反応が出ちゃうんだよなあ。序列とか根回しとかめんどくさ…。2025/05/13
Aby
7
久し振りに刊行された「農村社会学」.かつての「農村」は産業構造の変化と都市部の拡大により混住化が進んで,農村らしい農村ではなくなった.鈴木榮太郎のいう「村の精神」はどこへいってしまったのか……という,ところを論じてくれている.ありがたい.2024/07/11
そ吉
6
筆者は日本社会学会会長職にあるが、本書は学術書ではなく社会学を研究した筆者がファールドとした村に関しての随筆的な本である。 勿論、随所にある考察は先行研究の所在も明らかにしており、本書を入門書として村社会の構造を学ぶには良いだろう。 ところで、村の基底には封建的な搾取面のみではなく、奉仕による生活補償という保険的なものがあるという考えは現代ではボランティアなどの生活支援型のコミュニティに関する示唆ともなるかもしれないと思った。 ★★★☆☆2023/04/15
-

- 和書
- 禁煙学 (改訂5版)
-
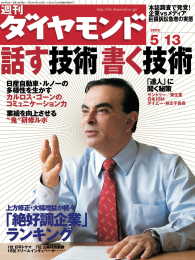
- 電子書籍
- 週刊ダイヤモンド 06年5月13日号 …