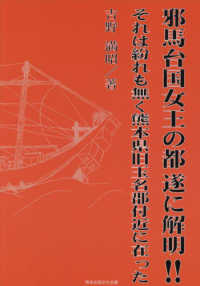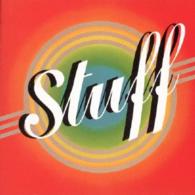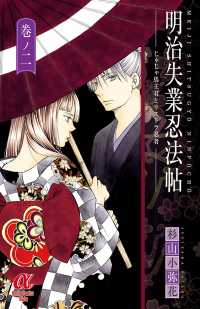出版社内容情報
米穀供給地として食を支え、近代以降は学都・軍都として人材も輩出、戦後は重工業化が企図された。度重なる災害も念頭に、中央と東北の構造を立体的に描き出す。
「東北」とは、幕末から近代において作られた言葉である。古代以来の律令制国たる陸奥・出羽二国の領域を「東北」と呼称して、地方の一体性を強調する現象が発生していくのは、主に近代以降のこと。時としてそこには「後進」や「周辺」の意味が込められている場合がある。本書は、この問題関心のもと、近世・近現代の東北史を三つの視点から描写する。一点目は、中央との位置。二点目は、各地との交流。三点目は、中央の影響力のもとでの地域の独自性である。
内容説明
「東北」とは、幕末から近代において作られた言葉である。古代以来の律令制国たる陸奥・出羽二国の領域を「東北」と呼称して、地方の一体性を強調する現象が発生していくのは、主に近代以降のこと。時としてそこには「後進」や「周辺」の意味が込められている場合がある。本書は、この問題関心のもと、近世・近現代の東北史を三つの視点から描写する。一点目は、中央との位置。二点目は、各地との交流。三点目は、中央の影響力のもとでの地域の独自性である。
目次
近世の幕開けと諸藩の成立
藩政の展開と藩主
社会の変容と諸藩
幕末の諸藩と戊辰戦争
明治政府と東北開発
近代日本の戦争と東北の軍都
戦時体制と東北振興
戦前戦後の東北の流通経済―百貨店を中心に
特論 奥羽の幕領と海運
特論 神に祀られた藩主―弘前藩四代藩主 津軽信政
〔特論〕近世後期の災害と復興・防災
〔特論〕東北開発と地域有力者
〔特論〕近代東北の教育と思想家
〔特論〕東日本大震災と歴史学―史料レスキューの現場から考える
〔特論〕東日本大震災と地域社会―福島県双葉郡富岡町の原発立地から全町避難を考える
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
てん06
qwer0987
アメヲトコ
fseigojp
つわぶき