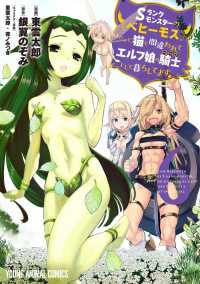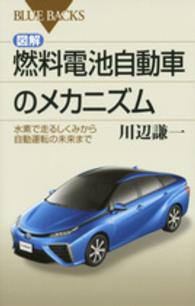出版社内容情報
辺境の地として倭人の大国に侵食された古代。豊かな天然資源が交易を支え、活発な交流が多様で独自性に富んだ地域を形成した中世。東北の成り立ちを読み解く。
東北史を三つの視点から読み解く。一つめは、近畿地方を中心に国家が形成されると、やがて国家的な境界が東北地方に形成されたこと。二つめは、境界領域としての東北地方で、人や物、言語、習俗、信仰などの交流が活発に行われたこと。三つめは、これまで一言で東北地方といってきた、その内側に多様性に富む地域が形成されていたということである。東北史を考えることは、現代日本の構造を明確化させることでもあり、逆に地域の主体性や独自性を示すことに他ならない。
内容説明
東北史を三つの視点から読み解く。一つめは、近畿地方を中心に国家が形成されると、やがて国家的な境界が東北地方に形成されたこと。二つめは、境界領域としての東北地方で、人や物、言語、習俗、信仰などの交流が活発に行われたこと。三つめは、これまで一言で東北地方といってきた、その内側に多様性に富む地域が形成されていたということである。東北史を考えることは、現代日本の構造を明確化させることでもあり、逆に地域の主体性や独自性を示すことに他ならない。
目次
東アジアの中のエミシ
国造制から国郡制へ―陸奥・出羽国の成立
城柵と戦争・交流の時代
城柵支配の変容と社会
古代から中世への変革と戦乱
平泉の世紀
関東武士の下で
奥羽と京・鎌倉―国人一揆を中心に
戦国期南奥羽の領主たち
北奥羽の戦国世界
〔特論〕北と南の辺境史
〔特論〕災害と社会の歩み
〔特論〕奥羽と夷狄島
〔特論〕奥羽の荘園と公領
〔特論〕伝承と物語
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
てん06
kenitirokikuti
翠
qwer0987
(k・o・n)b
-

- 洋書電子書籍
- グローバル・マーケティング(第3版)<…


![暮らしの小ワザ77 [バラエティ]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/48665/4866518456.jpg)