出版社内容情報
モンゴル帝国がユーラシアを征服し世界システムが成立する中、世界哲学はいかに展開したか。天や神など超越者に還元されない「個人の覚醒」に注目し考察する。
内容説明
一体化する世界における個をめぐる思考の全体像。
目次
第1章 都市の発達と個人の覚醒
第2章 トマス・アクィナスと托鉢修道会
第3章 西洋中世における存在と本質
第4章 アラビア哲学とイスラーム
第5章 トマス情念論による伝統の理論化
第6章 西洋中世の認識論
第7章 西洋中世哲学の総括としての唯名論
第8章 朱子学
第9章 鎌倉時代の仏教
第10章 中世ユダヤ哲学
1 ~ 1件/全1件
- 評価
-





akky本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
94
このシリーズは本当に授業を受けているような気にさせてくれます。じっくりと読むのがいいのでしょうね。非常に幅広に13世紀における世界の哲学に絡んだ話が門外漢のわたしにもわかる感じで説明されています。西洋ではトマス・アクィナスの「神学大全」を中心とした情念論や感覚論、中国の朱子学、日本では鎌倉仏教について理解が深まります。中世ユダヤ哲学ということでイスラム世界におけるユダヤ哲学がどのように生まれたかもわかります。佐藤優さんが宗教改革についてのコラムを寄稿されています。2025/07/03
to boy
31
十三世紀を中心に西欧、中国イスラム、日本、など世界の思想界を俯瞰した内容。経済が発達し都市が発達したこと、教会が告解を義務付けたことなどが個人の目覚めを促したことになるほどと思った。朱子学の説明はわかりやすくて納得。この時代西欧と日本の思想界で同じような動きがあった事に何か不思議な思いがしました。西欧中世の普遍論争とか認識論にはちょっとついて行けない。ただでさえ難しい哲学に神学が絡んできてなかなか理解できないです。2020/12/07
1.3manen
30
参考文献のガザ―リー『哲学者の自己矛盾』平凡社、2015年が何か気になる(106頁)。哲学者批判だから。怒り(傍点)という情念も気概的能力の重要なはたらき(119頁)。朱子学では、心は性と情けを統(す)ぶ(188頁から)。動詞で統合の統を「すぶ」というのは知らなかった。「ごったんふねい」(兀庵普寧)(219頁)は日本史図版の これ(『日本史 図版・史料読みとり問題集: 大学入学共通テスト・国公立2次・私立大対応』)に出てきたような? 他、預言とは、人間が自ら知性を高める能動的な行為である(242頁)。 2021/05/22
K
21
手放し気味だった本シリーズも、半分を迎えた。本書では、中世盛期、13世紀の世界の諸哲学が論じられている。はやりこの時期目をみはるものは、「普遍論争」である。実在論vs唯名論の構造が、かなり詳しく述べられていた。それ以外では、アリストテレス哲学が影響が強い時代だったことがうかがわれる。さらに、東洋に目を向ければ、朱子学の興隆、鎌倉時代の仏教など、ボリューム満点だった。私は、はやく近世以降をやりたいのだが、暗いイメージの中世にも世界全体に目をやれば、様々な哲学、思想、宗教が存在していたことがわかった。2021/04/11
しんすけ
20
今回も知られる哲学史ではない。しかし書かれていることのすべてが未知はない。 哲学とは今までは観てはいなかったものが、ここに集めらえたという印象も残る。 トマス・アクィナス以外は、そう言っても過言ではないのとさえ思う。 この時期は宗教においても大きな動きがあった。日本では鎌倉仏教、西欧では宗教改革の前史ととれる動きもみられる。 編者は偶然だろうかとも書いているが、社会構造の歪みが共通に露呈しだしていたのでないかと観ること可能なのではないか。 法然、親鸞、日蓮が、為政者の迫害下にあったことが、そこに重なる。 2024/01/04
-
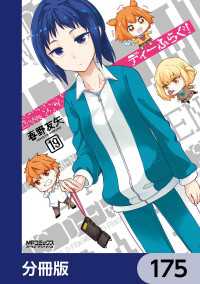
- 電子書籍
- ディーふらぐ!【分冊版】 175 MF…
-
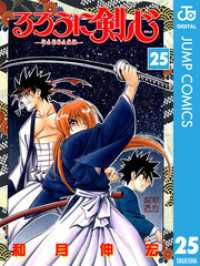
- 電子書籍
- るろうに剣心―明治剣客浪漫譚― モノク…




