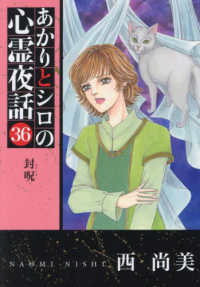出版社内容情報
「葬式仏教」との批判にどう応えるか。子育て支援、グリーフケア、アイドル育成、貧困対策。社会に寄り添う仏教の可能性を探る。
内容説明
地域社会の過疎化による仏教の衰退が問題化する一方で、二〇〇〇年代以降、仏教界では新しい世代による「仏教の社会活動・文化活動」の波が訪れている。本書では、子育て支援、アイドル育成、演劇活動、NPOとの協働、貧困問題、グリーフケア、ビハーラ(仏教版ホスピス)などの多種多様な活動を取り上げ、その社会活動の最前線を、当事者と研究者が協力して紹介する。現代社会に寄り添う仏教の新たな可能性を探る。
目次
第1章 なぜ、お寺が社会活動を行うのか?
第2章 貧困問題―「おてらおやつクラブ」の現場から
第3章 アイドルとともに歩む―ナムい世界をつくろう
第4章 子育て支援―サラナ親子教室の試み
第5章 女性の活動―広島県北仏婦ビハーラ活動の会
第6章 グリーフケア―亡き人とともに生きる
第7章 食料支援と被災地支援―滋賀教区浄土宗青年会のおうみ米一升運動
第8章 NPOとの協働から、終活へ―應典院の二〇年と現在、これから
現代仏教を知るためのブックガイド
著者等紹介
大谷栄一[オオタニエイイチ]
1968年東京都生まれ。佛教大学社会学部教授。博士(社会学)。専門は宗教社会学、近代仏教研究(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
西
16
お寺の可能性を感じる本。中でもおてらおやつクラブの活動は良いなと思う。自分が思っているより、貧困に苦しんでいる方は多いのだなと。そして真面目さゆえに周りに頼ることができない悲しさ。お寺を中心に、地域社会で助け合っていける関係性が出来ればいいなと思う。私は地元の、知り合いばかりの関係性が嫌で外に出たい出たいと思っていたが、今になってその地域性のありがたみもわかってきた。今更ともいえるけど。こういう本に出会えたこと、もっと言えば仏教に興味を持てたことも、観劇で訪問する應典院つながりで、そこに縁を感じる。2019/05/20
お抹茶
1
葬式仏教からの脱却を目指し,仏教の社会活動に奮闘する僧侶達の報告。お寺のお供えを貧困家庭へ分ける活動では,僧侶や檀信徒など自分達のことを考えてくれている存在を感じることが孤立解消の一助となる。お寺での子育て支援では,檀家組織を超えて若い親子と関わり合うことで,閉塞した状況を打ち破ることにもなる。僧侶が向き合うことを求められているのは,言葉に紡ぎえない嘆きに呼応し,聞き洩らさないこと。死別は,「会いたい」という本音と「会えない」現実世界との往来に折り合いをつけ,亡き人が「ともに在る」ことを確証する。2019/07/30
あしお
1
書いている人は浄土宗系の方々が多いようです。彼の宗派の上人さんは本当に人格・見識共にが高い方が多く、また人との繋がりを築くのが上手ですね。それと比べて、我が曹洞宗は比較的内向的な性格が強いように思います。それが「みんなでお念仏」と「壁に向かって坐っとれ」の教義の違いかもしれません。。曹洞宗の寺院にも色々とアイデアを出してイベントをしたりするお寺もあるのですが、地域の壁をでていけない感じの活動が多いです。色々と参考になり刺激にもなりました。2020/02/24
tecchan
0
家族形態の変化、葬祭簡素化、後継者難等々で今、お寺を取り巻く環境は激変。そうした中で、お寺の果たす社会的役割を見直そうという各地における僧侶・お寺の様々な取り組みを紹介する。2025/01/18
ばにき
0
寺院はコンビニより多いらしい。いろいろと社会活動していることがわかった。宗教だけでなく、伝統とも認知されているのがお寺の強み。伝統を守るための宗教活動、本当に必要としている人への教化活動に加え、社会活動の可能性を感じた。3つをバランスよくやっていくのがいいのかな、と。2021/07/09