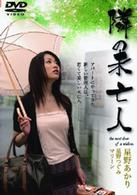出版社内容情報
近年「ADHD(注意欠如多動性障害)」と診断される大人が増えている。本書は、症状、診断・治療方法、他の精神疾患との関連などをわかりやすく解説する。
内容説明
今までADHD(注意欠如多動性障害)は、一般的に子供の「病気」とみなされてきた。しかし近年、ADHDと診断される大人が急増している。その数は成人の約3%(クラスに1人!)にも及ぶ。本書は、最近とみに注目されるようになってきた「大人のADHD」について、専門医が解説する一冊である。ADHDとは何か、特有の症状はどんなものか、ASD(自閉症スペクトラム障害)との相違点は何か、どんな治療法があるのか。この不思議な「疾患」について知るための、決定版といえる一冊である。
目次
第1章 ADHDとは何か
第2章 症状
第3章 社会生活
第4章 ADHDと他の精神疾患
第5章 ADHDとASD
第6章 診断
第7章 治療
第8章 衝動性・攻撃性
著者等紹介
岩波明[イワナミアキラ]
1959年神奈川県生まれ。東京大学医学部医学科卒。医学博士、精神保健指定医。都立松沢病院、東大病院精神科などをへて、2012年より昭和大学医学部精神医学講座主任教授。2015年より昭和大学附属烏山病院長を兼任、ADHD専門外来を担当。精神疾患の認知機能障害、発達障害の臨床研究などを主な研究分野としている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
京都と医療と人権の本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゆいまある
105
豊富な症例が挙げられているが、診断の根拠をどこにしたのか分かり難くい。発達障害はあらゆる精神疾患の温床になるので、オーバーラップは当然多くなるのだが鑑別することに力みを感じる(併存でいいじゃないか)。あとがきに、ADHDは時代を切り拓くと、美しいことを書いておきながら、本文に出てくるのはあんまり明るい人生送ってない人々。あと、家族がどのような支援をすればいいかなどの記載はなく、診察室の中だけしか見てない大学の先生らしい本だった。あとがきで高学歴女性に対する時代錯誤な偏見が爆発していて、不愉快であった。2021/08/11
のぶのぶ
34
仕事本。ADHDの特徴がよくわかった。思い浮かぶ顔がいっぱい。大人のADHDについて書かれていて、今後、心配だなあと思う顔もちらほら。大人のADHDは、誤診されていることも多く、根を辿っていくとADHDであることも多いようだ。根にあるものに対処していくことが大事なようだ。本人だけでなく、周りも理解していくことが大事なようで、そういうアプローチもあるようです。特性を理解し、こうするといいよとアドバイスをしていきたい。また、ADHDの方の魅力も体感しているので、うまく生かしていくことが大事なように思う。2017/04/02
けん
31
ADHD(注意欠如多動性障害)はその名の通り不注意と多動傾向を主な症状としている。生活に影響を及ぼすほどではないにしても、多くの人が「もしかして!」と思ってしまうかもしれない事例がいくつも記載されていた。本書を読むまで、ADHDに関してほとんど知識がなく、難しくて理解仕切れていない部分もあるが、知ろうとすること、理解しようとすることが大切だと思うので、もっと調べてみたい。2015/10/01
mio217
26
ADHD(注意欠如多動性障害)は小児に見られる発達障害の症状かと思いきや、大人にも数多く見られるという。主に、落ち着きがなくケアレスミスが多く物忘れが多いといった症状。実は私の身近にそうではないか?と思われる人がいたので読んでみた。この症状は投薬治療で改善されるそうです。あまりにも日常生活に支障をきたすぐらいの問題を多発するなら、精神科を受診する事も有なのですね。症状を受け入れれば、事は解決するのかもしれない。内容は難しいけど、興味深い本だった。2016/04/21
ぼんくら
26
2015年刊。ADHDの歴史、症状、併存する精神疾患、診断、治療について。具体例も交えながら網羅的に書かれている。最新の情報が載っているのがよい。薬についても詳しい。あとがきに、ADHDはトリックスターで、世界を変える力を持っているとあるが、そんな力いらないよな~2016/01/31