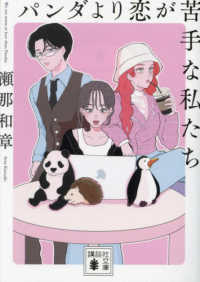内容説明
誰からも傷つけられたくないし、傷つけたくもない。そういう繊細な「優しさ」が、いまの若い世代の生きづらさを生んでいる。周囲から浮いてしまわないよう神経を張りつめ、その場の空気を読む。誰にも振り向いてもらえないかもしれないとおびえながら、ケータイ・メールでお互いのつながりを確かめ合う。いじめやひきこもり、リストカットといった現象を取り上げ、その背景には何があるのか、気鋭の社会学者が鋭く迫る。
目次
第1章 いじめを生み出す「優しい関係」(繊細な気くばりを示す若者たち;友だちとの衝突を避けるテクニック ほか)
第2章 リストカット少女の「痛み」の系譜(高野悦子と南条あやの青春日記;自分と対話する手段としての日記 ほか)
第3章 ひきこもりとケータイ小説のあいだ(「自分の地獄」という悪夢;「優しい関係」という大きな壁 ほか)
第4章 ケータイによる自己ナビゲーション(ケータイはもはや電話機ではない;「ふれあい」のためのメディア ほか)
第5章 ネット自殺のねじれたリアリティ(ネット集団自殺がみせる不可解さ;現実世界のリアリティの希薄さ ほか)
著者等紹介
土井隆義[ドイタカヨシ]
1960年山口県生まれ。大阪大学大学院人間科学研究科博士後期課程中退。現在、筑波大学大学院人文社会科学研究科教授。社会学を専攻。博士(人間科学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
coaf
31
これほどまでに衝撃を受けた本は初めて。若者たちの友だち関係を軸に、若者中心の社会問題にまで切り込む。共感する箇所があまりにも多くて、著者の若者への理解に驚いた。若者たちの感じる生きづらさの原因を鮮やかに解き明かす。本書を読んで新たな視点をいくつも獲得した。対人関係や生きづらさに悩む若者は是非。名著。どうして著者がここまで若者の気持ちを理解出来るのかと思えば、筆者自身も若者の気持ちを共有していたらしい。どうりで。この本の内容は実際に体験したことの無い人には本当の意味では理解出来ない。2012/06/26
ゆう。
29
若者が抱えている生きづらさ。関係性を築く上で、飾らない自分でいることが難しい。自分を確かめるために身体を傷つけ、血を見る若者。息苦しい社会は誰がつくったのだろう。私たち一人ひとりで成り立つ社会。優しさを強要するのではなく、自分でいられる居場所が必要だと思った。2020/06/20
めっし
29
現代日本の若者を論じた良著。「学校」という空間で一日の大半を過ごす生徒たちが、日々どのように人間関係で息苦しさを感じているのかという点を、様々な観点から指摘する。「空気を読め(KYなど)」「優しい関係」「むかつくといった生理的直観的言語」「島宇宙化する教室」「半カースト構造」など若者論を総括する「友だち地獄」。衝撃的な内容で、多くの示唆を得た。2012/07/16
テツ
25
誰も傷つけず、誰からも傷つけられない。集団の空気を読みそれを維持するためだけに行なわれる中身の無い会話。ハイデガーが説く空談そのままに行なわれるそれについての(というよりそれにより培われる脆弱なコミュニケーション能力か)問題提起。多層化した偽りだらけの人間関係を適当にやり過ごすスキルは社会人なら誰しも所有しているものだけれど、あまりにそれに慣れすぎると人間と関わる力が削ぎ落とされていくんだろうな。あえて空気を読まず集団の中でトリックスターとなる強さを身に付けている人間が群れのためには必要だ。2017/03/29
阿部義彦
24
ちくま新書、ネットの登場によって予め生きづらさをこじらせまくっている今の世代、思えば自分の若い頃は粗雑さゆえの逃げ場所がいっぱい用意されていたし、何でもマニュアル化すれば問題解決とする様な性急な傾向もなく、ある意味ドンくさく、手探りで時間を掛けて解決方法を探しても何にも言われなかったしそれが当たり前でした。「二十歳の原点」高野悦子と「卒業式まで死にません」南条あやとの日記の比較がその辺を余す所なく伝えていて興味深かった。2018/07/14
-
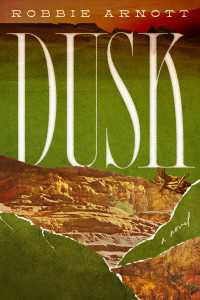
- 洋書電子書籍
- Dusk : A Novel
-

- 洋書電子書籍
- Executive Function …