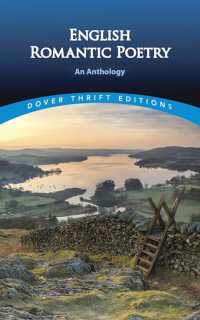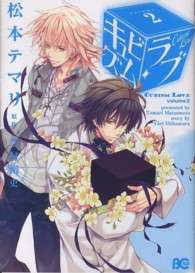内容説明
哲学の文章は「誤読」の可能性に満ちている。すべてを人生や道徳の問題であるかのように曲解する「人生論的誤読」、思想的な知識によってわかった気になる「知識による予断」、「答え」を性急に求めすぎて「謎」を見失ってしまう「誤読」、そして新たな哲学の問いをひらく生産的な「誤読」…。本書は、大学入試(国語)に出題された野矢茂樹・永井均・中島義道・大森荘蔵の文章を精読する試みである。出題者・解説者・入不二自身・執筆者それぞれの「誤読」に焦点をあてながら、哲学の文章の読み方を明快に示す、ユニークな入門書。
目次
第1章 「謎」が立ち上がる―野矢茂樹「他者という謎」(「答え」ではなく「問い」;「問い」というよりも「謎」 ほか)
第2章 “外”へ!―永井均「解釈学・系譜学・考古学」(解釈学;系譜学 ほか)
第3章 未来なんて“ない”―中島義道「幻想としての未来」(テーマ;概観 ほか)
第4章 「過去をいま引き起こす」ことはできるか?―大森荘蔵「『後の祭り』を祈る」(私の読み方の強調点;「酋長の踊り」という話の紹介 ほか)
著者等紹介
入不二基義[イリフジモトヨシ]
1958年11月11日生まれ。東京大学文学部哲学科卒。同大学院人文科学研究科博士課程単位取得。山口大学助教授を経て、青山学院大学文学部准教授。自我論・相対主義論・時間論等を主なフィールドとして、哲学をしている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
本屋のカガヤの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
WATA
69
大学入試の現代文の問題を哲学者が解くことで、哲学的な文章の読み方を伝授しようとする意欲的な1冊。この本の中で詳細に検討されている4つの文章はすべて高水準だが、その中でも第2章の永井均さんの文章が良い。また、それを解読する著者の解説の良さも抜群。まさかメーテルリンクの「青い鳥」から、こんなにも奥が深い哲学的時間論が展開されるとは思わなかった。同じ永井均さんの「子どものための哲学対話」でも少し触れられていた「家にいた鳥が<もともと青かった>ってことにあとから変わった」という言葉の意味がやっと理解できた。2014/06/03
メタボン
12
☆☆☆☆ 誤読をテーマとした哲学の本。スリリングな論の展開で、読むことの愉楽に浸った。たまには難しい文章で頭の中をかきまわさなければだめだなと思った。2015/05/06
Bartleby
11
現代文の大学入試問題で哲学する、という企画が面白そうで手に取った。テキストは、永井均、野矢茂樹、中島義道、大森荘蔵。テーマは主に時間論。もちろん、本書は設問に対する批評にもなっている。模範解答作成者はたじたじだろう。なにより、文章(とくに哲学的文章)を精読するプロセスを詳細に示してくれていて、たいへん参考になった。大学受験生にもおすすめ。2022/09/18
袖崎いたる
9
哲学的な言い方に対して論理的に読み込んでいくスタンスから解答を導き出すという大学入試が、哲学を誤読しがちであるという事態に哲学者がこだわりを持ったのが本書。たしかに哲学史上、哲学書は誤読の系譜を記述できる。パッと浮かぶのでもハイデガーの『存在と時間』に対するサルトルやレヴィナスの誤読は有名だ。そうした誤読は原理的に、哲学的な意味があると見る著者はまともだろう。そしてそのモデルとしての大学入試問題というわけである。面白いのは問題の解説文を書いた人が思想系の知識があるこどでテキストを誤読することがあった点。2017/08/17
みどるん
7
入試問題の哲学的文章を徹底的に読み込む本。内容が難しいものでも手取り足取り教えてくれるので、ただ読むだけで自分だけでは得られなかった視界が開けます。考えるっておもしろい。2014/07/29
-
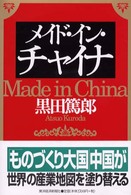
- 和書
- メイド・イン・チャイナ