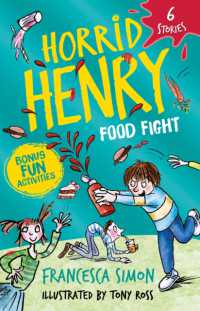内容説明
江戸の教育といえば、「寺子屋」「読み書き算用」だが、その内実はどのようなものであったのか。寺子屋では子ども一人一人に応じて、社会に出て困らないような、「一人前」になるためのテキスト(手習教本)が用意され、そうした文字教育は非文字の教育(しつけ・礼儀)と不可分のものだった。地域において教育を担ったのは、名望家の文人たちであり、そのネットワークが日本中に張りめぐらされ、教育レベルを下支えしていた。その驚くべき実像を、近世教育史の第一人者が掘り起こす。
目次
プロローグ 「教育の時代」としての江戸時代
第1章 江戸時代の文字文化(寺子屋の時代;村の寺子屋;町の寺子屋;礼儀作法をしつけた寺子屋;師弟は三世の契り)
第2章 江戸時代の非文字文化―家と地域の教育(親をしつける―大原幽学の教育;一人前にする―「若者組」の教育;家を守る―放蕩息子を勘当する)
第3章 江戸の教育ネットワーク(『論語』が常識の時代;『小学』が寺子屋師匠のバックボーン;知のネットワーク)
エピローグ 庶民皆学の行方
著者等紹介
高橋敏[タカハシサトシ]
1940年生まれ。1965年東京教育大学大学院文学研究科修士課程修了。現在、国立歴史民俗博物館名誉教授。文学博士。専門は近世教育・社会史、アウトロー研究(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Shoko
24
江戸の教育力の源泉は地域の教育力にあった。各地に情熱を燃やした寺子屋の師匠がいた。読み書きと一体となって子どもに礼儀をしつけること。「礼儀なき子どもは読み書きを学ぶ資格なし」が鉄則。今の学校や先生にこの情熱を求めるのは酷か。若者組の説明にあったこの文で昨今のニューストピックとしてよくあがる家庭内暴力や虐待の問題を思い浮かべた。「厳しい現実ではあるが、ヒトは家族の愛だけでは一人前になれない。他人との共同社会生活の中でしか人間にはなれないのである。」学問も大事。でも、それ以上に大事なことも教えられていたのだ。2019/12/18
イボンヌ
10
日本人が勤勉だった頃の時代のお話しです。 日本人にとって、長い間中国が全てのお手本だった事もわかりました。2018/08/08
isao_key
10
江戸時代の寺子屋の実体や庶民たちの教育について言及している。寺子屋について、これまで読み書きの識字率を飛躍的に向上させた立役者であるという先入観が強く、全体像は明らかにされないところがあったが、実は読み書きと一体となって、子どもに礼儀をしつけることも狙いにあったという。実例として駿河国駿東郡吉久保村の寺小屋塾則が挙げられている。これを読むと、朝はお天道様、家のご先祖様を拝み、父母に挨拶の礼をして朝飯を食べ寺小屋へ出かけ、教場に入ると正座して畳に手を付いて額をさげて心を静め深く礼をしてから席に着くとある。2016/05/23
Susumu Kobayashi
5
江戸時代、幕府は庶民の教育には関与せず、庶民は自分たちで教育を施すしかなかった。当時の寺子屋教育、非文字文化(しつけ)、江戸の教育ネットワークについて書かれている。四書五経にふりがなをふって読みやすくした『経典余師』という本がベストセラーとなり、『論語』が常識となったという。とりわけ、江戸時代に知のネットワークが形成された点は興味深かった。江戸時代から明治時代へのスムーズな移行は高い教育レヴェルを抜きにしてはおそらく考えられないだろう。2017/01/16
nobinobi
4
識字率が高かったと言われている江戸の教育に興味があり読む。個人的には、放浪者を家庭教師やら、村の相談役やらとして迎え入れる文化が面白いと感じた。現代だったら、怪しい人というくくりで相手にすらしないだろう。以下は備忘録。 −子どもを大人にする一人前の教育は、文字文化と非文字文化を一体化して実に円滑に機能していた。家族と共同体の子育て、寺子屋での読み書き算用の学習、若者組での一人前の鍛錬、それぞれが重複・錯綜しながらも相互に連携し、一貫した組織をつくりあげていた。2017/02/12