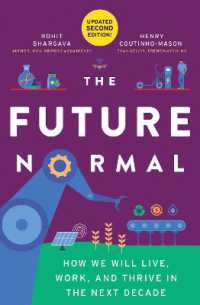出版社内容情報
日本人の食文化に広く浸透する豚。イスラム圏、ヨーロッパなどの世界各地ではその豚がどう思われ、どう扱われているのか。豚を通して見える世界の文化、宗教、政治、歴史とは?(解説/麻木久仁子)
内容説明
牛や鶏と並んで日本の食文化に広く浸透する“豚”。この生き物は世界の国々でどう思われ、どう扱われているのか。コーランで禁忌とされる豚、食糧難解決のため大量飼育される豚、風刺画の中の豚。その存在は神聖か、不浄か。著者は真実を見極めるため、イスラム圏、旧ソ連圏を経て極寒の地、シベリアへ。豚を通して見えてくる文化、宗教、政治、歴史とは?独自取材で挑む渾身のノンフィクション。
目次
序章 豚に会いたい―ワールド
第1章 豚と人間、そして神―チュニジア
第2章 豚の歩いてきた道―イスラエル
第3章 検索キーワード・豚―日本
第4章 豚になったスターリン―リトアニア
第5章 幸福の豚、不幸の豚―バルト三国
第6章 豚をナイフで殺すとき―ルーマニア
第7章 子豚のホルマリン潰け―モルドバ
第8章 子豚たちの運命―ウクライナ
終章 素足の豚―シベリア
著者等紹介
中村安希[ナカムラアキ]
ノンフィクション作家。1979年京都府生まれ、三重県育ち。2003年カリフォルニア大学アーバイン校、舞台芸術学部卒業。09年『インパラの朝』で第7回開高健ノンフィクション賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ぶち
58
ピンクの可愛い表紙。でも、内容は広く、重い内容です。豚という家畜は、人間との付き合いが最も長い肉です。食べる選択と食べない選択と、生きるためには食べるしかなかった人々。工業製品のように生産された豚と、手塩にかけて育て感謝をこめて命をいただく豚と。愛される豚と、豚と揶揄される嫌われ者の政治家。豚を通して見えてくる文化、宗教、政治、歴史を、ぐいぐい読める筆致と描写で明らかにしていきます。普段、あたりまえのようにしてスーパーに並ぶ豚肉を見ていますが、この本で考えざるを得ないようになりました。2018/11/09
わんこのしっぽ
33
こんなタイトルの前を通りすぎることなんて出来ない(笑)もう少し砕けた内容かと思ったら予想外に硬派でタイトルとのギャップが^^;中東からイスラエルにかけては宗教と豚との関わり。東欧からロシアにかけては旧ソ連と東欧との関わり、そしてシベリア抑留の北の果てまで。いつしか豚の話を離れてしまった感はありますがそれぞれの民族、歴史を垣間見ることが出来て興味深かった。2015/04/20
Yuichiro Komiya
14
豚を追う旅。地域毎に豚との関わり方というのは違う。今の日本は、食肉加工の過程が表に出ないため、豚肉を食べるのに普段は何の罪悪感も感謝も抱きにくい。実際に生きている豚が殺され、解体されるところを見れば、肉を食べるという行為にもっと何か思うところが出てくるのかもしれない。2019/03/02
piro
13
再読。豚を追い求めチュニジア、イスラエル、バルト三国、ウクライナ、そして極寒のシベリアなどを巡る一冊。『それは、宗教を隔てる境界線であり、人々の属性を示すアイデンティティであり、豊かさと同時に、欲望の象徴でもあった。』ややまとまりに欠けるものの、豚を食べる人々と禁忌としている人々の考え方の違いや、歴史的背景といったものが少し見えた気がして興味深かったです。無駄を削ぎ落とし、研ぎ澄まされた文章からは、著者が見聞きした世界の様子が生き生きと伝わって来る様でした。因みに私はポークカレー派です。2017/11/16
ジュースの素
12
豚肉というのはけっこう難物で国や地域によっていろんな差別や愛情を受けている。さすがに世界を廻った中村安希には各国に知人がいるなぁとまず驚き。豚の事を調べる旅に友人の力やツテは欠かせない。豚ほど宗教や政策に振り回される肉はない。イスラムはさて置き、イスラエルの禁忌も非常に多い。羊や鶏に比べて傷みやすいが、牧場が不要なので飼いやすく早く成長するので効率がいい。日本国内でも西と東では豚肉の用途や扱いに大きな差が! さすがに宗教絡みは無いけど。2017/09/19