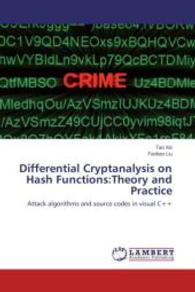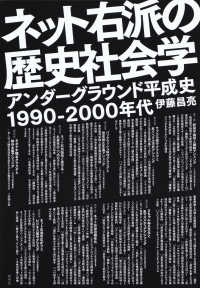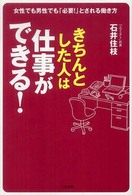内容説明
格差社会の果てにワーキングプアや生活保護世帯が急増中、と言われる。しかし本当にそうか?バブルの時代にも貧困問題はあった。ただそれを、この国は「ない」ことにしてきたのだ。そもそも、貧困をめぐる多様な議論が存在することも、あまり知られていない。貧困問題をどう捉えるか、その実態はどうなっているのか。ある特定の人たちばかりが貧困に苦しみ、そこから抜け出せずにいる現状を明らかにし、その処方箋を示す。
目次
1章 格差論から貧困論へ
2章 貧困の境界
3章 現代日本の「貧困の経験」
4章 ホームレスと社会的排除
5章 不利な人々
6章 貧困は貧困だけで終わらない
7章 どうしたらよいか
著者等紹介
岩田正美[イワタマサミ]
1947年生まれ。中央大学大学院経済学研究科修士課程修了。博士(社会福祉学)。日本女子大学教授。研究テーマは、貧困・社会的排除と福祉政策。『戦後社会福祉の展開と大都市最底辺』(ミネルヴァ書房)で第2回社会政策学会学術賞、第4回福武直賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
テツ
20
いい年こいた大人が自分が繰り返してきた山のような選択の果てにどうにかなってしまうのはある程度仕方がないと思うけれど、生まれのせいで親の貧困をそのまま受け継いでしまうこどもが存在することは本当にどうにかしなければならないと思う。まともな経済感覚も生きるためのリテラシーもない人間に育てられるなんて虐待でしかないよな。学歴や収入がある階層で固定されてしまうのは、それらの大切さを知らない人間がこどもを育ててしまうからだ。どんな場所に生まれても教育の大切さを教えて、それを受ける権利を与えられる社会であって欲しい。2021/12/17
大島ちかり
17
私たちは何が出来るのか。まだまだ分かりません。ずっと研究をしている岩田さんにも。政治が悪い、私たちの意識が低いというのは分かっているのに。でも消費税10%の問題もあって、このごろマスコミで毎日のように取り上げられるようになり、広く現実が知られるようになってきてるので、社会現象として政治的にも議論されるといいなと思います。貧困を減らすことが日本の経済を復興することにもつながるのに。残念な社会です。2014/11/09
林 一歩
13
対岸の火事では、もうないんだよね。2014/11/09
キムチ
13
現在、すっかり社会的認知を得ているワーキング・プア、ホームレス、生活保護に対する行政の根幹を知るにはとてもいい教科書だと思う。学生向きと思うのは専門用語や概念が多用されているから。とはいうものの、一人歩きを始めている上記3つの基礎を押さえるにはよい。この分野の一人者である岩田氏、現在行政の分野でも重鎮であり戦後の流れを良く解説してある。
無識者
12
貧困に陥る人とそうでない人、貧困に陥っても脱出できる人とそうでない人といる。貧困から脱出するとき多くは貯金を切り崩したり、親戚の支えによって切り抜ける。逆に言えば固定した貧困層は湯浅氏の表現を借りると溜めがない人々なのである。日本の社会保障は主に保険の形態をとっていて再分配機能が低く、貧困からの脱出が困難である2016/05/18