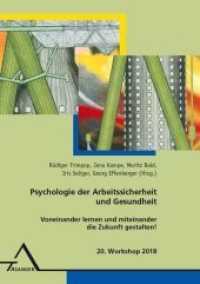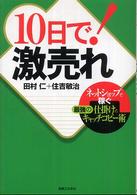内容説明
本書では、ロボットを、その歴史から紐解いて、現在をつぶさに考察し、この二一世紀の未来を見据える。それも、技術史という立場からではなく、実際に現場でロボットを研究開発している研究者としての立場から、今後のロボット開発の方向を探るという目的のために歴史を見つめ直す。
目次
第1章 ロボットへの夢とあこがれ
第2章 ロボットへのあくなき挑戦
第3章 ロボットをつくる思想
第4章 ロボティクスの誕生
第5章 人間を助ける目と手
第6章 ロボットと人間を一体化する―テレイグジスタンス
第7章 ネットワークでロボットを結ぶ―アールキューブ
終章
著者等紹介
舘〓[タチススム]
1946年東京生まれ。東京大学工学部計数工学科卒。同大学院工学系研究科修了。工学博士。MIT客員研究員、東京大学先端科学技術研究センター教授などを経て、現在同大学院情報理工学系研究科教授。専門はロボット工学、バーチャルリアリティ、計測制御工学。医療福祉ロボット、テレイグジスタンス、アールキューブなどの研究を通し、次世代ロボット研究を牽引するとともに、人とロボットのよりよき共存のための方法論を構築している
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
Koning
19
ロボットの歴史(それこそイーリアスだのの昔から)を語りつつ、初期の単機能のロボットから続く現代のロボットのシステムの哲学とでもいうかサブタイトル通りつくる哲学とつかう知恵という事もかなり気にして書かれてて宜しいんじゃないかと。先日ISO13482が正式に発行されて気になってたところで、最終的には生活支援ロボットという物がどう生活の場に入って来るか?という事を考えるにはいい読み物だった。パワードスーツの系統とリモコンロボットの系統、そしてアンドロイドやらの系統とそれぞれに役割と利用目的が違って発展(続く2014/09/08
★★★★★
4
ロボットをめぐる文学や思想から、(2002年当時の)最新技術までカバーした、「ロボット」についての入門書。門外漢としては非常に面白く読みました。著者自身の研究の自画自賛はちょいとうっとうしいけれども。2010/11/16
Norihumi Yahata
1
今までのロボットの歴史とこれからあり得るであろうロボットの姿を分かりやすく書いてあった。ロボットを制作する技術も大切だか、そのロボットをどう使うかと言う倫理も大切だと理解できた。2014/04/04
静
1
ロボット史をさらって最後にロボットがどういう方向に行くかみたいな話をしてる。ただの入門書だからそれでいいんだろうけど、サブタイトルがひっかかる。どの辺が『つくる哲学』だったんだろうか。ロボットは何より安全でなければならないという著者の信念が貫かれてたとは感じるけど、それってむしろ技術と倫理の問題だろう。著者の安全であるべきという信念を考察してたら『つくる哲学』だったかもしれないけど。あと、義手とか盲導犬ロボット、特に、災害時危険なところで作業するロボットって、今こそ必要とされてると思う2012/03/14
いちはじめ
1
NHKでオンエアされた「人間講座」のテキストがベースらしく、比較的判りやすい。自分の研究分野の説明が多めなのは仕方ないか2002/03/25