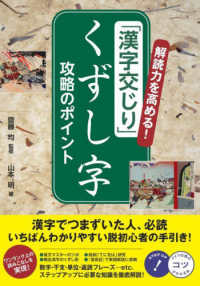内容説明
座敷わらしが住む旧家に生まれた少女には、常に目に見えないものとの心の交流があった。「あるとしもなき」存在の妖精を30余年の歳月をかけて追いもとめ、指折りの研究者となった著者が、生まれ育った土地、自然、生活、環境、学問研究の背景、人との出会いの中に妖精学への萌芽をさぐる試み。妖精版「失われし時を求めて」。
目次
第1章 生まれた土地と自然(神秘の日光、那須の伝説;育った城下町、百年の商家;座敷わらし、環境の変化;お神楽で学んだ神話、グリム童話 ほか)
第2章 実存のはかなさと遙かなるものへの憧れ(戦争体験、ヨーロッパへの憧れ;劇、架空の実世界;菊池寛と民映、ヘリックの糸;川上澄生の版画、浜田庄司の益子焼 ほか)
第3章 束の間の幸福、妖精の救済(短い幸福、その瓦解;息子をイギリスに学ばせて;学匠日夏耿之介先生;恩師島田謹二先生 ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
榊原 香織
64
妖精学、の大家の自伝。 色々有名人とのふれあい、川上澄夫に英語習った、というのが驚いた。版画家と思っていた。(”邪宗門”そうですよね)2021/11/12
paxomnibus
3
著者の思い出語りではあるが、日本の歴史を幼い女の子の視点から成長に伴いつつ振り返り見るのが実は面白い。英国の妖精譚に触れるというのはかつて教養がなければできないことだったが、それのできる環境がどういうものだったか伝わってくるのだ。石岡瑛子展を見に行った時にも感じたし、映画で見たオノ・ヨーコや草間 彌生等、過去の日本で自己主張を貫いた女性の芸術家は大体生家が裕福で立派な教育を受けている。恵まれた環境があってこそ才能が開花、いや、周囲から認めて貰えるのだろう。生まれによってそれが決まるのは、実は今も同じだが。2021/07/17
j1296118
1
妖精の話……ではなく、妖精ものの研究・著書豊富な作者の自伝、思い出話。所々で妖精・妖怪にちょっかいをかけられている風な話を挟むため「ではなく」と言い切ったものでもないが、題から思ったのとは違う内容で、毎度の如くそれはそれで楽しめる我が節操無さが幸い也。 戦場ヶ原の伝説に始まり幼少の頃や学生時代、連帯保証人になった災難や水木しげる・荒俣宏の助力、天野喜孝のステンドグラスを設えた妖精美術館建設、その評価というか不理解等々。 不自由になった際水木しげるに贈られた目玉の親父に体重を預け、ねずみ男を傍らに休む作者2015/03/07
ちいくま
1
妖精についての本と信じて借りたら、著者の半生が延々とつづられてた… 一部口述だからなのか、私の理解力が足りないのか、事実の前後関係とか分かりにくい部分多数で不思議な読書となりました。昭和初期のお金持ちお嬢様の麗しい生活はファンタジーを読んでるかのようで、それなりに面白かったですが。 ちくまプリマーブックスのラインナップ、興味大。2014/06/16
-
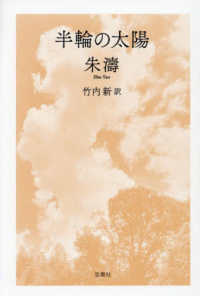
- 和書
- 半輪の太陽