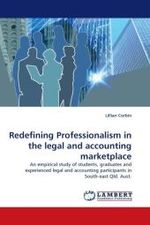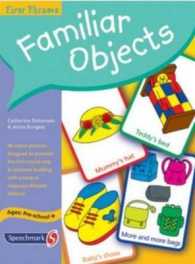内容説明
《ハーメルンの笛吹き男》伝説はどうして生まれたのか。13世紀ドイツの小さな町で起こったひとつの事件の謎を、当時のハーメルンの人々の生活を手がかりに解明、これまで歴史学が触れてこなかったヨーロッパ中世社会の差別の問題を明らかにし、ヨーロッパ中世の人々の心的構造の核にあるものに迫る。新しい社会史を確立するきっかけとなった記念碑的作品。
目次
第1部 笛吹き男伝説の成立(笛吹き男伝説の原型;1284年6月26日の出来事;植民者の希望と現実;経済繁栄の蔭で;遍歴芸人たちの社会的地位)
第2部 笛吹き男伝説の変貌(笛吹き男伝説から鼠捕り男伝説へ;近代的伝説研究の序章;現代に生きる伝説の貌)
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
まーくん
136
再読。30年ぶり内容は全く記憶なく改めて読み直し。グリム伝説集によると1284年、北ドイツのヴェーゼル河畔の町ハーメルンに現れた不思議な男(まだら色の服を着た笛吹き男)に引き連れられて130人の子供達が町を出て消え失せた。ゲッチンゲンの文書館で古文書分析に没頭していた著者は<ハーメルンの笛吹き男>の研究書に出会う。この話は単なるメルヘンなのか、それとも何らかの史実に基づくものなのか?背景となる中世ヨーロッパの社会史を深く紐解きながら真実を追う。この時代の領邦国家としてのドイツ、庶民の生活が見えてくる。2022/12/12
へくとぱすかる
107
1284年6月26日に発生した、子どもたちの大量失踪事件。伝説を探求する過程で、中世ドイツ世界の差別の諸相にたどりつく。政治・経済が中心の歴史からは事件の追究は困難で、まして700年以上の歳月の壁がある。しかし、事件の真相よりも、なぜ人々はこの伝説にこだわったのかを読み解くことで、きれいごとで済まされない過去の重みを感じることができる。それでも知りたい。真相は何だったのか?2016/01/30
こきよ
80
ヨーロッパ中世史を、法制史や政治史、更には社会史的な外殻よりも潜在し、濃密な民衆史的目線で追った作品。民間伝承(所謂伝説の類も)を探索することの一種快楽にも似た知的興奮を堪能出来る反面、追えば追うほどその対象の生命力を弱めているという氏の苦悩も見て取れる点に於いて、研究、引いては学問全体にも一石を投じている作品である。2014/08/15
ヨーイチ
69
著者は高名な歴史学者。名前だけは知っていた。ハーメルンの笛吹き男、笛を吹いて鼠を駆除してあげたが最後には村の子供たちを連れて行ってしまうって童話は子供の頃から知っていたが、そのハーメルンでの伝承調査から始まって、他の研究を紹介しつつ、伝説の裏側に潜む中世ドイツ人の世界を著者なりの推理を交えて読者に伝えてくれる。日本で言うと鎌倉時代・蒙古襲来頃ドイツの小都市ハーメルンで子供たちが集団でいなくなったという事実はあったらしい。著者の姿勢は史実もさる事ながら、その逸話を今日まで長持ちさせた「チカラ」 続く2019/09/26
藤月はな(灯れ松明の火)
57
文学フリマで購入した、田井ノエル先生の『愚裏夢は夜に嗤う』がハーメルンの笛吹き男をモチーフにしていたので懐かしくなり、再読。黒死病による死への暗示、少年十字軍への熱狂、奴隷商人による誘拐など、様々な憶測が語られつつも多くの謎を残したハーメルンでの少年少女失踪事件。築によって貧富の差が線引きされた上に身分も固定化され、立身出世が困難だった時代。それ故のハレの日の狂乱や自分達より下だと見なした階級への迫害、抵抗としての伝承化等に複合的な要因は余りにも人間的だからこそ、私たちはこの事件に惹かれるのかもしれない。2025/10/18