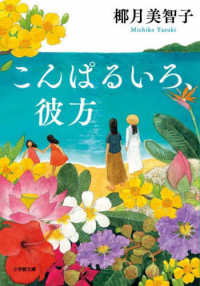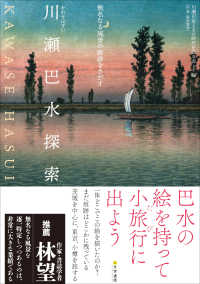内容説明
《パラノ人間》から《スキゾ人間》へ、《住む文明》から《逃げる文明》への大転換の中で、軽やかに《知》と戯れるためのマニュアル。―現代思想の最前線を疾走する若き知性がドゥルーズ=ガタリ、マルクスなどをテクストに語る《知》的逃走のための挑発的メッセージ。
目次
逃走する文明
ゲイ・サイエンス
差異化のパラノイア
スキゾ・カルチャーの到来
対話 ドゥルーズ=ガタリを読む
マルクス主義とディコンストラクション
ぼくたちのマルクス
本物の日本銀行券は贋物だった
共同討議マルクス・貨幣・言語
ツマミ食い読書術
知の最前線への旅
N・G=レーゲン『経済学の神話』
今村仁司『労働のオントロギー』
広松渉『唯物史観と国家論』
栗本慎一郎『ブタペスト物語』
山本哲士『消費のメタファー』
柄谷行人『隠喩としての建築』
山口昌男『文化の詩学1・2』
蓮実重彦『映画誘惑のエクリチュール』
1 ~ 1件/全1件
- 評価
-





読書という航海の本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ehirano1
80
「逃げたら負け」や「逃げることは恥」という価値観を粉砕する本書。我慢したあげく病んでしまうのであれば本書の逃走論はまさに福音書となり得ると思います。2025/03/29
ころこ
47
浅田彰の仕事って読者はどの様にとらえているのか、実は私もよく分かりません。『構造と力』が教養主義的であり、それはまたヘーゲル的なパラダイムの中にあることは論を待たないと思います。他方で、本書は教養主義とは正反対の議論が行われています。仲正昌樹は、本書を真に受けてフリーターを選択した当時のスキゾ・キッズに対して、いったい著者は何と言うんだろうと批判しています。著者はその問いかけからも逃走するのでしょうが、では、なぜその著者が『構造と力』を書かなければならなかったのか。結局、還暦を迎えた著者がここまで何を残そ2021/04/23
みのくま
17
人間には二つの型がある。過去の全てを積分=統合化し背負うパラノ(=偏執)型と、そのつど時点ゼロで微分=差異化するスキゾ(=分裂)型の二通りだ。現代の高度資本主義社会(=クラインの壺)は、人間をあらゆる問題が強迫神経症的に追い詰めて行く。このような状況に対し著者は、パラノ的に「闘争」するのではなく、スキゾ的に「逃走」しろ!と言う。マジメではなくフマジメに生きよ、と。その時に必要なのがユーモアだ。やってくる諸問題をはっきりと認識しつつ、ふとそれをはぐらかし、肩をすくめて、もう一つのレベルに移ってみせるのだ。2018/05/13
koji
16
単行本刊行から37年、ずっと気になっていました。当時大学生で、ポスト構造主義、マルクス主義、記号論と、華やかに難解な言葉を駆使するニューアカと呼ばれた著者に憧れたものです。(本文にある)スキゾ・キッズや「逃げろや逃げろ」は、今でも記憶に残ってます。さて読んでみて。生産型資本主義の行き詰まりから大衆資本社会への移行という時代背景があり、特に西武百貨店の広告戦略を哲学的に肯定する論理に見えます。その後のバブル、その崩壊を考えると納得がいかない所はありますが知的刺激は十分受けました。長年の宿題を漸く提出しました2019/12/08
nobody
15
皆様、ぜひとも「目新しい理論に大急ぎでツバを付け、その断片的引用をファッショナブルな彩りとして著書の商品価値を高めるというやり方」とも「理論的内容を断片化し、ミスリーディングな使い方をするの」とも全く無縁で、「ラカンやクリステヴァへの言及にいたっては、論理的脈絡が全く欠けているために、読者を途方にくれさせる」ことも全くない、「『読者の自律性を尊重する』がゆえにあえて『教育的』な書き方を避けたのだというのは、未整理の材料を投げ出したことへの言い訳にはならない」という指摘など全く当たらない本書をご堪能下さい(2019/08/02
-
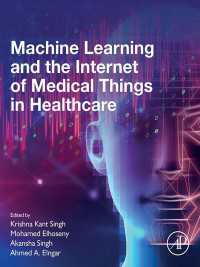
- 洋書電子書籍
-
医療のための機械学習とIoMT
…
-
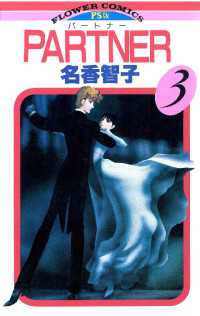
- 電子書籍
- PARTNER(3) フラワーコミックス