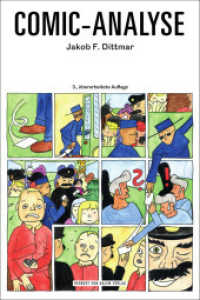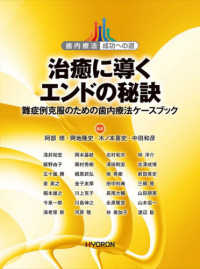出版社内容情報
健康をめぐる社会のしくみは、人々の自由をどう変えるのか。セン、ロールズ、ヌスバウムなどの議論を手掛かりに、現代社会に広がる倫理的な難問をじっくり考える。
内容説明
パンデミックにおける行動制限から肥満対策、健康格差や自己責任論、健康増進にかかわるナッジの問題点に至るまで。健康をめぐる社会のしくみは、人々の自由をどのように変えるのか。選択すべきは介入か、それとも個人の自律か―。高度化する健康管理の技術を注意深く読み解きながら、健康を守る社会の仕組みと個人の生き方の複雑な関係をめぐる問いにじっくり向き合う。自分自身で考え、共に生きるための倫理学。
目次
序章 公衆衛生倫理学の問題関心
第1章 肥満対策の倫理的な課題
第2章 健康の社会経済的な格差の倫理
第3章 健康増進のためのナッジの倫理
第4章 健康をめぐる自己責任論の倫理
第5章 パンデミック対策の倫理
終章 自由としての公衆衛生へ
著者等紹介
玉手慎太郎[タマテシンタロウ]
1986年宮城県生まれ。現在、学習院大学法学部政治学科教授。東北大学大学院経済学研究科博士後期課程修了。博士(経済学)。専門は政治哲学・倫理学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
どんぐり
81
公衆衛生における倫理的正当性を検討するのが「公衆衛生倫理学」。なじみのない学問分野だが、直近の例では、コロナウイルス感染症感染症が蔓延したときにとられたワクチン接種、隔離政策、行動制限が問題群としてあげられる。国家の介入の度合いがモニタリングから情報提供、リスクコミニュケーション、選択の誘導と制限(行動の制限)へと増していった。それらを倫理的正当性の面から考える視座を与えてくれる。そして本書で総論的に論じているのが、健康格差、健康政策としてのナッジの功罪、健康責任論、ケイパビリティ・アプローチ。→2024/11/13
けんとまん1007
45
公衆衛生をテーマとしているが、それに留まらない。ものごとを考えるにあたり、倫理学の視点からどう捉えるか。自分自身、倫理学といいながら疎い世界ではある。それでも、公衆衛生・健康が扱われているので、考えやすくなっている。一見、良さそうなこと(これ自体、曖昧ではある)でも、一歩引いて考えることから始める。これまでも、時間を置いて考え直すことはやってきたつもりだが、視点をもう少し、拡げれそうだ。ナッジについての論評も、なるほどなあ~と思う。2025/11/05
Iwata Kentaro
15
たまたま誘導され見つけた本。めちゃくちゃ名著。著者の本は初めてだが実に素晴らしい。コロナの時代に感染症の「専門家」に失望した人は多いと思うしそれはまあ申し訳ないと思うけど、僕らは僕らで多くの「社会科学」の専門家に失望したこの数年だった。「その程度の見識」で自分の欲望正当化するための浅い議論かよ、と何度思ったことか。本書は違う。サブタイトルの「どこまで」が象徴的だし(介入すべきか、が命題ではない)、「ジレンマ」の扱いもフェア。倫理学に心理学(世論)がどこまで絡むか、の考察も面白かった。公衆衛生の人は必読。2023/02/26
たか
9
3章のナッジ・4章の自己責任論への考察が特に良かった。ナッジは低コストかつ選択の自由を奪わない点で優れており、メリットが強調されることが多い。しかし当人の最善の利益という枠組を踏み外し、当局の意向やある特定の道徳的価値観を達成するために使われる危険もある。この点セイラーとサンスティーンの立場の違いが、経済学と法哲学の方法論をそのまま反映していて面白い。自己責任論は批判者自身の弱さを認められないことの裏返し、であればコントロール不可能性は応答になり得ず、弱さを認め合い連帯することが解決につながる。2023/04/30
おやぶたんぐ
7
健康増進、感染症対策等の公衆衛生実現のためには、公権力による個人の自由や自律への介入が不可避とすれば、その介入についてどのように考えていくか。筆者による分析と視点が提示される。自由の多様性を前提にして、自由のための公衆衛生、自由を通じた公衆衛生を説く立論は説得的ではある。問題は、具体的にどのように実現していくか、だろう。まさに問われているのが少数派の自由であるだけに、手続的にも実体的にも容易ではないと思われる。2023/07/31
-
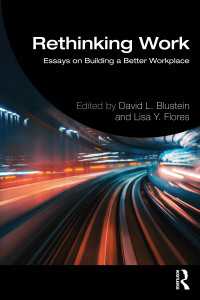
- 洋書電子書籍
- 仕事をつくりなおす:よりよい職場のため…
-
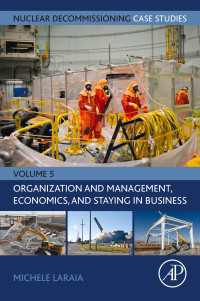
- 洋書電子書籍
- 原発廃炉事例研究:組織・管理・経済・事…