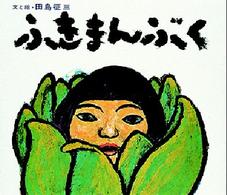出版社内容情報
トランプ政権との対立、コロナウイルスの蔓延、デジタル化の波、格差の拡大――、理念と現実の狭間で民主主義の根幹を支えるアメリカ図書館界の奮闘を活写する。
内容説明
格差の拡大に直面する現代社会において、図書館はいかなる役割を担っているのか。「無料貸本屋」と揶揄されるイメージとは異なり、移民受け入れや崩壊するコミュニティの再生、オバマケアの窓口、デジタル化の最前線と、様々な場面で民主主義の根幹を支える拠点となってきた。予算をめぐってトランプ政権と対立するなど数々の危機を乗り越え、理念と現実の狭間でもがくアメリカ図書館界の知られざる奮闘を活写する。
目次
序章 図書館がつくる民主主義
第1章 地域変革の触媒としての図書館
第2章 博物館・図書館サービス機構の誕生
第3章 インターネット時代の図書館
第4章 博物館・図書館サービス機構の発展
第5章 国と地方をつなぐ州図書館局
第6章 トランプvsアメリカ図書館
著者等紹介
豊田恭子[トヨダキョウコ]
1960年、東京都生まれ。ビジネス支援図書館推進協議会副理事長。北海学園大学非常勤講師。お茶の水女子大学卒業。出版業界紙記者を経て米国留学。シモンズ大学(ボストン)で図書館情報学修士号取得。帰国後、国際金融機関J・P・モルガンの日本支社でビジネスリソースセンターを立ち上げ、その後ゲッティ・イメージズの画像データベースやNTTデータの環境データベースの運営に関わる。2009年に札幌に移住。2022年まで広報エージェンシー、バーソン・コーン&ウルフに勤務(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
koke
スターライト
たろーたん
yurari
ミガーいち