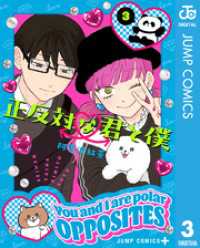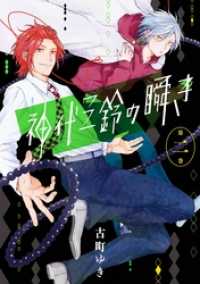出版社内容情報
芭蕉の真骨頂は歌仙の捌きにこそある。芭蕉にとって歌仙とは、現実の世界から飛翔し風雅の世界にあそぶことであった。「七部集」を読みなおし、蕉風の核心に迫る。
内容説明
古池の一句で蕉風を揺るぎないものとし、「おくのほそ道」において「かるみ」という人生観に至った芭蕉はその後、さらに高く飛翔して風雅の世界に遊ぶ。芭蕉にとって風雅とは、いかなる境地であったのか。みずからの真骨頂と自負した蕉門歌仙を深くたずね、「虚に居て実をおこなふ」芭蕉の核心に迫る。
著者等紹介
長谷川櫂[ハセガワカイ]
1954年熊本県生まれ。東京大学法学部卒。読売新聞記者を経て、創作活動に専念。「朝日俳壇」選者、サイト「一億人の俳句入門」で「ネット投句」「うたたね歌仙」主宰、「季語と歳時記の会(きごさい)」代表、俳句結社「古志」前主宰、東海大学特任教授。『俳句の宇宙』で第十二回サントリー学芸賞受賞。第五句集『虚空』により第五十四回読売文学賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件