出版社内容情報
日本特有の習俗である「立ち読み」。一体いつ、どこで始まったのか? その歴史を丹念に辿ると、江戸から明治にかけての「書物の近代化」、そして「読者」の誕生が見えてくる! 国立国会図書館でレファレンス担当を15年務めた著者がその技術を尽くした野心作
内容説明
かつて洋行知識人は口々に言った―「海外に立ち読みなし」。日本特有の習俗「立ち読み」はいつ、どこで生まれ、庶民の読書文化を形作ってきたのか?本書はこれまで注目されてこなかった資料を発掘し、その歴史を描き出す。明治維新による「本の身分制」の解体、ニューメディア「雑誌」の登場、書店の店舗形態の変化…謎多き近代出版史を博捜するなかで浮かび上がってきたのは、読む本を自ら選び享受する我々「読者」の誕生だった!ベストセラー『調べる技術』著者がその技を尽くす野心作。
目次
零 立ち読みは日本だけ?!―「出版七つの大罪」の筆頭
一 江戸時代の読書―立ち読み前史
二 立ち読みが成立する条件
三 大正七年、宮武外骨の証言
四 書店でない「雑誌屋」
五 「立ち読み」の意味を整理する
六 「立ち読み」という言葉はいつからあったのか
七 江戸の「立ち見」から「立ち読み」の発生まで―立ち読み通史1
八 書店が「開架」したいきさつ―立ち読み通史2
九 「雑誌の時代」とその終わり―立ち読み通史3
十 「立ち読み」に似て非なるもの
著者等紹介
小林昌樹[コバヤシマサキ]
1967年東京生まれ。図書館情報学を研究するかたわら近代出版研究所を主宰し、年刊誌『近代出版研究』編集長を務める。慶應義塾大学文学部卒。国立国会図書館で15年にわたりレファレンス業務に従事、その経験を活かした『調べる技術』が3万部を超えるヒット作となる。コミケにも精力的に出店している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
- 評価
本屋のカガヤの本棚
-
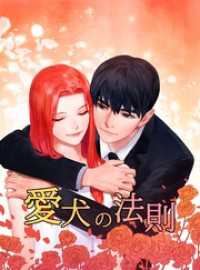
- 電子書籍
- 愛犬の法則【タテヨミ】第55話 愛犬は…




