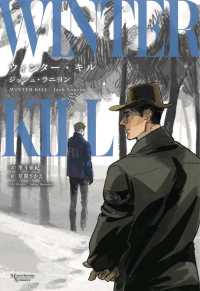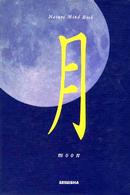出版社内容情報
東日本大震災・原発事故をめぐる膨大な情報を精緻に解析、その偏りと格差、不平等を生み出す社会構造を明らかにし、災害と情報に対する新しい視座を提示する。
内容説明
東日本大震災・原発事故後、私たちはおびただしい量の情報に曝された。錯綜する情報は人びとの不信を誘発する一方、時間とともに被災者を置き去りにして移ろい、結果として社会的弱者を生み出していった。本書では、3・11後のマスメディアおよびインターネットの膨大な情報を精緻に解析、その偏りと格差、不平等を生み出す社会構造を明らかにし、「災害」と「情報」に対する新しい視座を提示する。
目次
序章 おびただしい情報とどう向き合うか(情報の洪水のなかで;本書の視点)
第1章 災害弱者―3・11被害とその背景にある社会(現代社会におけるリスク分配と不平等;災害と災害弱者 ほか)
第2章 情報弱者―震災をめぐる情報の格差(被害格差、経済格差、情報格差―情報をめぐる二つの格差;震災・原発事故をめぐる情報格差 ほか)
第3章 震災後3カ月間の情報多様性(メディア上の議題を捉えること;情報空間の多様性―情報の渦のなかで ほか)
終章 「私たちが持つべき視点」の獲得に向けて(再び、弱者に関して;「いま議論すべきこと」は誰が決める?―議題設定と議題構築 ほか)
著者等紹介
田中幹人[タナカミキヒト]
1972年静岡県生まれ。国際基督教大学教養学部理学科卒、東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻生命環境科学系博士課程修了(博士(学術))。現在、早稲田大学大学院政治学研究科ジャーナリズムコース准教授。(社)サイエンス・メディア・センターリサーチマネージャー
標葉隆馬[シネハリュウマ]
1982年宮城県仙台市生まれ。京都大学農学部応用生命科学科卒、同大学院生命科学研究科博士課程修了(博士(生命科学))。専門は科学技術社会論、科学計量学。現在、総合研究大学院大学先導科学研究科「科学と社会」分野助教
丸山紀一朗[マルヤマキイチロウ]
1987年東京都生まれ。早稲田大学政治経済学部経済学科卒、同大学院政治学研究科ジャーナリズムコース修士課程修了(修士(ジャーナリズム))。現在、(株)キャリアブレイン勤務(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
takizawa
忍
鎌倉 幸子
1.3manen
kozawa
-
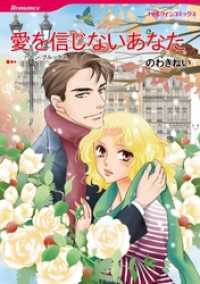
- 電子書籍
- 愛を信じないあなた【分冊】 9巻 ハー…
-

- 和書
- 旅行 日経産業シリーズ