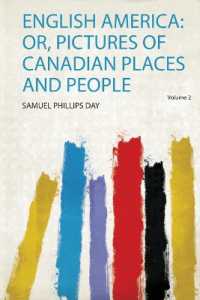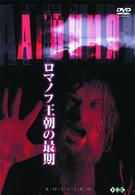内容説明
つくられた“女らしさ”の幻想を砕き、女性の生き方の原点を求めた世界的なベストセラー、不朽の名著リバイバル。
目次
満たされない生活
職業婦人から主婦業へ
女性の危機
女性解放の闘い
「フロイトの精神分析」の影響
女性の役割
女らしさのための教育
女性を誤らせたもの
消費の女王
“主婦業”は職業ではない
性の問題
人間らしさを奪う“収容所”
自己の確率
新しい生活設計
女性解放運動の実践の中から
著者等紹介
フリーダン,ベティ[フリーダン,ベティ][Friedan,Betty]
スミス女子大学卒。カリフォルニア大・バークレイ校大学院で心理学専攻。NOW(全米女性連盟)を組織。女性解放運動の指導者として活躍
三浦冨美子[ミウラフミコ]
日本女子大学卒。メリーランド大学を経て、州立サンフランシスコ大からM.A.(英米文学専攻)。慶応義塾大学名誉教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
みゃーこ
47
すばらしい。当時の女性はこの一冊で目からうろこが落ちて暴走してブラジャーまで焼いたという。力強い女。アメリカ女性運動の神。第2次世界大戦後のアメリカのフェミニズム運動「第二の波」の草分け的な存在。この人のせいで人生変えられ、世界が揺れ動いた。この時代ってほんと公民権運動、社会運動がほんとに活発だったんだろうなあ。わかりやすい敵があちこちに居て戦っていた。このくらいの一冊の小爆弾が何度も世界を変えてきたことを歴史は語っている。2015/05/08
柳瀬敬二
8
60年代以降のフェミニズム運動の火付け役となった一冊。家庭的な主婦像がもてはやされた二次大戦後のアメリカでは、多くの女性が大学卒業前に結婚するようになり、学業を途中で放棄する事例も増えていた。だが、家庭に入り社会との繋がりを失った彼女達は心身のバランスを崩していく。青年期を経る前に主婦になってしまった彼女達は夫や子ども、間男を通してしか自己表現できず、彼女達からの精神的圧力が家族にも悪影響を及ぼす。 専業主婦ではやはり人は幸せにはなれないらしい。たとえ自分の実存を見出すのが茨の道だったとしても。2016/05/27
kenitirokikuti
5
本書は2004年改訂版。以下、1973年の増補版の補章から引用。〈女性解放運動のなかに、男性蔑視の要素を誰が、何のために持ちこみ、操作したのかは、私にはわからない。分裂した会員には極左分子がいたようだし、同性愛者に転向させるために女性解放運動を利用した者もいたようだし、…女性の正当な怒りを、性の階級闘争のレトリックを用いて、理路整然と表現しようとした者もいたようだ。〉2017/07/09
orange21
3
歴史書として読めるが現代ですら切実な問題がある。30年代には自立していた女性が60年代には家事育児セックスだけが役割の主婦を理想とされ初婚年齢が劇的に下がっていたなど面白い。原因はフロイト理論の無批判な援用や戦争、消費財広告のジェンダーステレオタイプなど色々。ただ古い本だなと感じる部分も多く、同じくフロイトを援用し現代では少々問題がありそうな同性愛者についての言及や「成長した」などの定義の不明さ、また女性に自立を促しつつ家事コストについては効率化省力化で乗り切ると言うばかりで男性負担コストはゼロ。2020/04/07
ヒナコ
3
郊外に住む中産階級の白人主婦が物質的に満たされながらも言葉にできない不満を抱えているのはなぜかという問いに、その原因を女性の職場からの排除に求め、女性の雇用市場への再参入を解決として提示したという意味で、大きなインパクトを持った作品。 しかし、再就職が個人の意識の問題に還元されるので、ジェンダーが階層性を伴ったシステムであるという視点が全くない。ミレットの『性の政治学』と本書との差異はジェンダーの強制的反復性を強調と無視に有るだろう。本書の半分は頑張れという説教であるが、単にそう読んでしまうのは勿体ない。2018/02/23
-

- 電子書籍
- 男子禁制ゲーム世界で俺がやるべき唯一の…
-
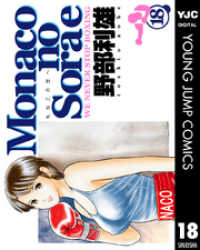
- 電子書籍
- Monacoの空へ 18 ヤングジャン…