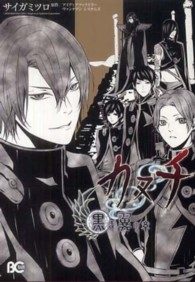内容説明
頭の中の「使っていないソフト」を動かす。「自分の命が何より大事」というのは本当だろうか?「論理的」イコール「正しい」とは言えないのではないか?「人は死なない」と考えることもできるのではないか?論理に縛られて「テンプレート化した発想」から抜け出すための12講。
目次
自分の頭で考えるには?
テクノロジーを疑う
ぐらぐらしたものをそのまま捉える
「カネを中心にした発想」から抜け出す
文学は何の役に立つのか?
「神の手ゴール」はハンドでは?
同じことを考えつづける力
「じゃあ、猫はどうするんだ」と考える
それは「中2の論理」ではないか?
飲み込みがたいものを飲み込む
収束させない、拡散させる
考えるとは、理想を考えること
著者等紹介
保坂和志[ホサカカズシ]
1956年、山梨県生まれ。早稲田大学政経学部卒業。93年『草の上の朝食』で野間文芸新人賞、95年『この人の閾(いき)』で芥川賞、97年『季節の記憶』で谷崎潤一郎賞、平林たい子文学賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
i-miya
38
2013.07.10(読んだわけではありません、日経新聞夕刊、夕刊文化欄から) (「考える」には言葉の論理は不要) (時間かけ、「感覚」磨こう) 「考えるとは、言葉で論理を組み立てることではない」「わかった、と思わず、じっくりと世界に触れあうこと」 近くのおいしい中華料理店、その店主、僕の『考える練習』を見て、息子に、お前、考えることができるか」と。 しかし、苦手なのではない。2013/07/10
井月 奎(いづき けい)
35
考えることは結構しんどいです。考えること自体も面倒臭いですし、しかも考え続けるといろいろな、ともすると相反する結果が出て、しかも両方ともがいい考え、ということもあり、我と我が心を悩ませます。でも、考える、思考する、それが人を人たらしめているのです。あっちの考えがこっちの思いと結びつき、そっちの気持ちがあそこの思いとぶつかる。それが人を深くして綾なる心を紡いでいくのだと思います。人が自分の色合いで、香りで生きていくことが世界を豊かにしていくのです。簡単なことであるはずがありません。そう思わせてくれる本です。2019/09/19
パスティル
21
書店で目につき、図書館で借りた本。脳がしびれる感じです。考えること、自分の言葉で自分の意見を言う。日々の生活へ大いに活かせそうです。2015/03/28
kubottar
20
文学を学びたくなります。グローバリゼーションとはアメリカの都合のいいルールを受け入れるということなら、日本はその逆張りをすべきとは面白い考え方ですね。それにはやはりビジネス書を読んで上司に取り入るテクニックを覚えず、文学をやってその逆をいったほうがいい。2022/10/16
Meme
17
自分の思考のフォーマットに目を向けろ。思考のテンプレートから抜け出せ。本書のキーメッセージはこれだと思います。なんてことは、きっと保坂さんに怒られるんでしょう笑 本を要約して分かった気になるなんて、受動的に刷り込まれた現代の思考の仕方なんだから、もっと自由にしなよ。て。分かろうとしなくていいんだよって。もしビビビっときたら、分かったってことだから。て。この本は何回も読まないとなあ。2023/05/18
-

- 和書
- 古手川祐子写真集