出版社内容情報
Google、Dell、Microsoftなど世界有数の外資系企業で20年間活躍した著者が教えるインサイドセールスの極意
水嶋 玲以仁[ミズシマ レイニ]
著・文・その他
内容説明
訪問の必要がないから、2倍の商談数がこなせて、しかも定時に帰ることができる。そんな究極の営業術「インサイドセールス」について、最新かつベストな手法を紹介します。
目次
1 インサイドセールスに必要な「協創と自律性の高い組織」(どうしてうまくいかない?ウチのインサイドセールス;セールス組織にアジャイルを取り入れる)
2 成約率を高めるインサイドセールスはいかにして築かれるのか?(脱・アポ取り集団!マーケティングと営業を巻き込むインサイドセールスをめざす;予想を超える急成長。ISチームの意識が変わった!;アジャイルな行動を可能にするユーザベースの組織風土)
3 インサイドセールス先進企業に聞く営業組織と育成の正解(ISとFSのコンビで、長いリードタイムを乗り切る―株式会社HDE;インサイドセールスでもクロージングできる―ベルフェイス株式会社;ツールをフル活用し、人にしかできない業務に集中する―株式会社マルケト)
著者等紹介
水嶋玲以仁[ミズシマレイニ]
グローバルインサイト合同会社代表。東京都出身。北海道大学経済学部卒。日本メーカーから外資系保険会社に転職し財務部長まで務めた後、デルコンピュータに転職しコンシューマー部門のジェネラル・マネージャーとなる。以降、インサイドセールスの実務全般について、20年に及ぶ経験を持つ。そのうち16年間は、世界有数のIT企業でB to B及びB to Cのインサイドセールス、営業チームの発展と管理業務に携わる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かいてぃ〜
mkt
前田まさき|採用プロデューサー
牧神の午後
masa
-
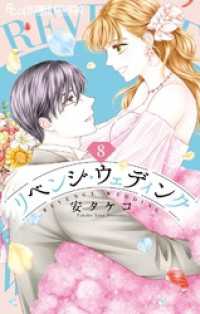
- 電子書籍
- リベンジ・ウェディング(8) フラワー…
-
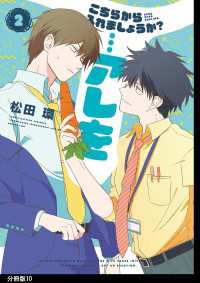
- 電子書籍
- こちらから入れましょうか?…アレを 分…
-
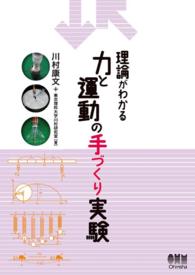
- 電子書籍
- 理論がわかる 力と運動の手づくり実験
-
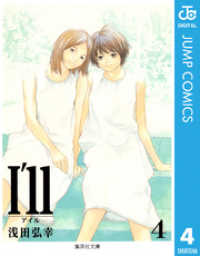
- 電子書籍
- I’ll ~アイル~ 4 ジャンプコミ…





