出版社内容情報
〈秀吉の死から、関ヶ原合戦、大坂の陣へといたる「慶長」という時代の20年間を、京都の公家や僧侶の日記などの同時代史
料から再検討〉〈京都東山に造立された大仏(大仏殿と本尊)の変遷を追うことでうきぼりとなる、豊臣と徳川との関係〉
20年続いた慶長年間(1596~1615)は、豊臣政権から徳川政権へ移行した時期で、日本史上のターニングポイントといえる時
代です。この時代は、関ヶ原合戦から大坂の陣へ至る「戦間期」ととらえられたり、自由であった民衆の世界が強化される封
建制のなかに閉ざされていく時代ととらえられることがありました。しかし、同時代の史料(公家や僧侶の日記など)からは
そうしたことは読み取れず、むしろ過ぎ去ろうとしない戦国の記憶、秀吉の治世のレガシーへの拒否感、その被害を最小限に
抑えてくれるかもしれない徳川への期待などが垣間見えます。あえて武家側からの視点とは距離をおき、京都東山に造立され
た大仏(大仏殿と本尊)の変遷を座標に据えて、慶長時代を再検討します。
内容説明
江戸時代は京都・伏見からはじまった。秀吉の死から、関ヶ原合戦、大坂の陣へといたる「慶長」という時代の20年間を、京都の公家や僧侶の日記などの同時代史料から再検討。
目次
第1章 「関東と京都の御弓箭」としての関ヶ原合戦(秀吉没後;京都からみた関ヶ原合戦)
第2章 豊国臨時祭と大仏(失われゆく大仏;豊国臨時祭)
第3章 「関東と京都の御弓箭」続編としての大坂の陣(失われた大仏をもとめて;京都からみた大坂の陣)
著者等紹介
河内将芳[カワウチマサヨシ]
1963年、大阪府生まれ。奈良大学文学部史学科教授。京都府立大学文学部文学科を卒業後、甲南高等学校・中学校教諭。その間に京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了、京都大学博士(人間・環境学)取得。京都造形芸術大学芸術学部歴史遺産学科准教授を経て、現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ほうすう
浅香山三郎
田中峰和
Abercrombie
-

- 洋書
- Дрm…
-
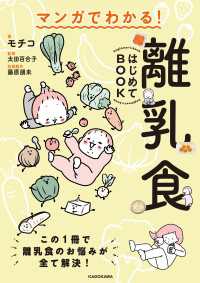
- 電子書籍
- マンガでわかる! 離乳食はじめてBOO…





