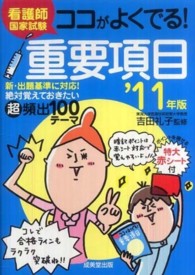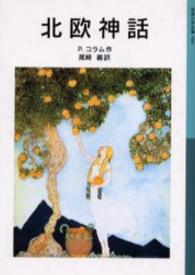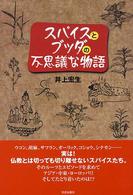出版社内容情報
数寄者のほか、女性や文化人などを含め、54名100余点の近代茶杓を紹介、その魅力にせまる。あわせて、蒐集品なども掲載。〈近代茶杓を通して知る、数寄者たちの交遊〉
〈近世から近代へ連綿と続く茶杓史の全貌がわかる〉
「茶杓は人なり」と称せられるように、そのシンプルな形の中に、作る人・作らせる人の美意識や人柄が映し出されています。
本書は、近代茶杓の礎となった近世茶杓を通した茶人往来を回顧し、三井財閥を支えた益田鈍翁を中心とする東西の近代数寄者たちが削った茶杓のほか、女性や文化人・芸術家などの作を含め、54名100余点の近代茶杓を紹介、その魅力の正体にせまります。また、茶杓以外の自作作品や蒐集品なども掲載することで、当時の数寄者の茶とはどのようなものであったのか、その一端を垣間見る内容となっています。
MIHO MUSEUM[ミホミュージアム]
編集
池田瓢阿[イケダヒョウア]
監修
目次
ごあいさつ 近代数寄者と茶杓
近代数寄者の茶の湯(熊倉功夫)
竹茶杓の魅力(池田瓢阿)
図版(近代以前の茶杓―贈り筒を中心に;益田鈍翁―近代数寄者の大立者;益田鈍翁を取り巻く関東・中京の数寄者による茶杓;女性による茶杓;関西における数寄者の茶杓;文化人の茶杓;茶杓とは)
総論 茶杓概論―近代の茶杓への道(池田瓢阿)
著者等紹介
池田瓢阿[イケダヒョウア]
竹芸家。昭和26年(1951)、東京都生まれ。武蔵野美術大学卒業後、竹芸の道に進む。祖父である初代は益田鈍翁より「瓢阿」の号を賜わり、2代目・瓢阿である父も鈍翁より薫陶を受けた。平成5年(1993)、3代目・瓢阿を襲名。古典の基本をしっかりと押さえつつ、竹芸の新しい可能性を探って精力的に活動し、日本橋三越本店において定期的に個展を開催。また、竹に関する茶道具や民俗などの研究に力を注いでいる。現在、竹芸教室「竹樂会」を主宰するとともに、淡交会巡回講師、淡交カルチャー教室講師、三越カルチャーセンター講師、NHK文化センター講師などをつとめる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。