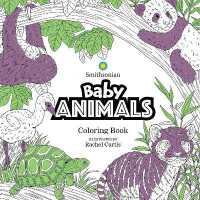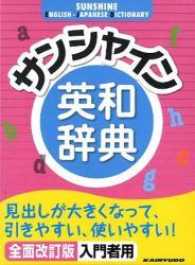出版社内容情報
機能と装飾性を追求した結び方、花むすび。現代にも息づく美しい結び方や四季を彩る結びを復元・解説するほか、くらしの中で楽しめる花むすびの応用法も紹介。
内容説明
日本の伝統文化が息づく能や狂言、いけばな、香、茶の湯の装飾を華やかせる四季の“花結び”を紹介。自然に対するあこがれを、わずか一本のひもが作りあげる四季のかたち。
目次
四季の花結び(梅結び;匂い梅結び ほか)
京都の祭りにみる結びのかたち
封じ結び・その他の結び(草の封じ結び;封じ結び ほか)
現代の結び・さまざま
結び解説(下結び;総角結び ほか)
著者等紹介
田中年子[タナカトシコ]
花結び作家。日本結び文化学会理事。滋賀県に生まれる。1964(昭和39)年から1991(平成3)年まで橋田正園氏に師事し、茶道(石州流清水派)花結び(飾り結び)を修得、花結び作家として独立。東亜三国結展6回出展、むすび文化展5回出展、小笠原庭園美術館(北九州市)「日本の結び用と美」協力出展、岐阜県瑞浪市(半原版画館)・滋賀県秦荘町・土山町・彦根市・大阪府羽曳野市・奈良県新庄町・東京畠山記念館で「田中年子花結び」展開催、NHK文化センター後援「ジャパン・フェスティバル」に5回参加。NHK文化センター京都、朝日カルチャーセンター京都で講師を務めるほか、東京・静岡・岐阜・大阪・滋賀の各教室で指導。滋賀県在住
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
本の紙魚
1
いくつか借りた紐結びの本の中で、具体的な結び方の説明が割合と多く、下結び、総角結び、梅・桜・桔梗結び、匂い梅結び、楓結び、かたばみ結び、とんぼう結び、五枚笹結び、草の封じ結び、千代久封じ結びが載っている。結び方が載っていない雪待笹結びや桃結びも可愛くて、紐の色や仕服の布も結び方に合わせていて見ているだけで心が華やぐ。一つ一つマスターするのは難しそうだし、解説によるとそもそも茶道具の仕服は他の人にはわからないような結び方をすることが常だったとか。異物混入を警戒してというところ当時の茶人たちの生活が思い浮かぶ2021/12/31