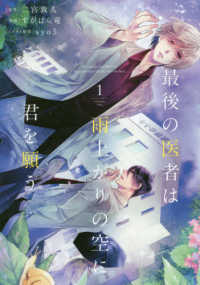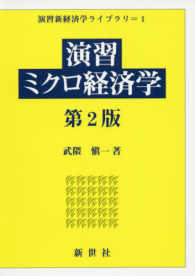出版社内容情報
世界にも愛好家が増えてきつつある「盆栽」について、その歴史をひもとき、成り立ちをわかりやすく紹介。図版多数。
内容説明
世界の“BONSAI”その歴史を探る。盆栽はいつから日本の伝統文化になったのか。歴史をひもとき、織田信長や徳川将軍家、明治天皇や大隈重信らの愛好ぶりを紹介。盆栽ミニ用語集/鑑賞のポイント/盆栽展・美術館・庭園ガイド付き。
目次
第1章 「鉢木」と「盆山」(織田信長の「盆山」狩り;吉田兼好と「鉢木」 ほか)
第2章 徳川将軍の植木棚をさぐる(江戸の園芸文化;徳川家綱と盆山献上 ほか)
第3章 「盆栽」の誕生(煎茶の流行と「文人盆栽」;盆栽園の起源 ほか)
第4章 近代の盆栽愛好家たち(盆栽愛好の広がり;皇室と盆栽 ほか)
第5章 盆栽の器と飾り方(盆栽の器;染付の鉢 ほか)
著者等紹介
依田徹[ヨダトオル]
1977年、山梨県生まれ。東京藝術大学大学院美術研究科芸術学専攻、博士後期課程修了。美術博士。さいたま市大宮盆栽美術館学芸員を経て、現在は東海大学非常勤講師。専門は日本近代美術史、茶道史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
にがうり
11
盆栽をビジュアル的にイメージすることはできても、「盆栽とは何か?」と問われると、うまく答えられない人がほとんどではないでしょうか。本書はタイトルの通り、盆栽の誕生から現在に至るまで、歴史的な変遷をたどりながら素人にもわかりやすく解説しているので、盆栽を体系的に理解したい人におすすめです。盆栽にも流行があり、戦国武将や江戸時代の徳川家が愛した盆栽が、現在の盆栽とは趣の異なるものだっという史実に驚きました。2014/05/30
とりもり
6
盆栽の歴史がよく分かる良書。人の一生よりもずっと長生きする盆栽は、名品と言われてもその時代の流行によって常に手を加えられて、その姿を変えながら受け継がれていくというのが非常に面白い。盆栽と言えば、何と言っても人工的に幹を曲げた模様木が連想されるが、それとて好まれなかった時期があるというのが意外だった。鉢にも流行りがあったりと、想像以上に奥深い盆栽の世界。昭和記念公園に盆栽苑があるみたいなので、今度行ってみよう。★★★★☆2017/10/10
或るエクレア
6
盆栽に似たようなものは古来からあったけど、茶の湯とともに発展していって明治に移る頃に、技工を凝らして大きく曲げたものから自然にあるような美へと変わった辺りが盆栽の誕生らしいです。物よりも見る人の意識の変化が重要ってことですかね。2015/07/10
HMax
3
日本の文化に最敬礼。 盆栽始めようかな。2014/07/31
AYA
2
図書館の本。渋い。でも盆栽の歴史を知ることができるとともに、歴史上の人物の盆栽との関わりが知れて面白い。2021/04/14
-
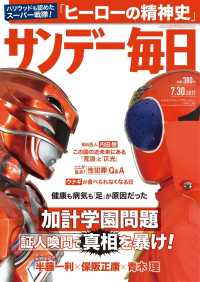
- 電子書籍
- サンデー毎日2017年7/30号