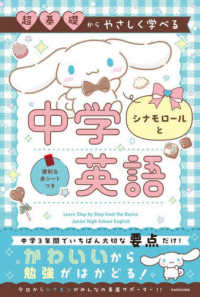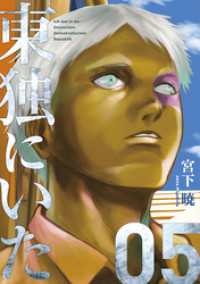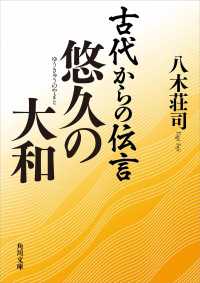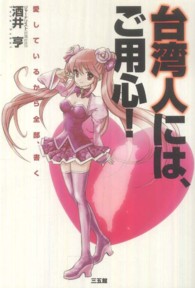内容説明
月・鶯・ほととぎす・梅・桜・風・雨・涙・こころ・露・雪…、古典詩歌に現れ、日本人の美意識の規範となった19の《ことば》をとりあげ、そのイメージがどのように形成されたかを明らかにする。日本の詩歌のことばは、古代以来、中国の詩文の影響下にあったが、その受容と展開の実態を《和漢比較的》な視点で解説する。表現の実例として掲げられる古典詩歌の引用には、すべて現代語訳を付し、出典を明示した。
目次
1 光り輝くものたち―沈黙の秩序
2 鳥の声と花の香―花鳥表現のウチとソト
3 彼方からの訪ない―習合的受容
4 たぎる思い―抒情の構造
5 移ろいと永遠―色の美学