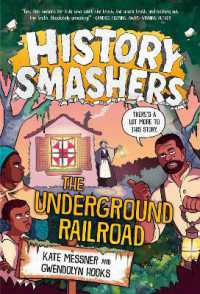内容説明
恩讐を超えて、新たな日韓関係構築のための糸口を探る―植民地下における社会事業とは何だったのか。植民地支配の一環として導入された救護法や救貧事業、施設を「社会事業」と呼べるのだろうか。本書では社会事業施設(主として隣保施設)の設立と社会事業家の活動内容、その本義について様々な文献・資料を読み解き考察した一労作!
目次
序章―社会事業史の視点から植民地統治期を捉えて見ると―
1章 近代社会における隣保館事業の思想的意義
2章 朝鮮における社会事業の始まり
3章 社会事業法による地域社会の統制
4章 社会事業施設の設立動向
5章 社会事業の財源内容
6章 京城府内の隣保館の性格分析
7章 方面委員と町洞総代の活動内容と役割
8章 民族同化に対する社会事業家、篤志家の本義
著者等紹介
天城寿之助[アマギトシノスケ]
1961年、鹿児島県(徳之島)生まれ。韓国史研究家。大韓民国、ソウル市立大学校人文学部国史学科卒業。大学院修了。東亜大学校史学科博士課程単位取得退学。東亜大学校経営大学国際観光通商学部招聘教授を経て帰国。帰国後は学校(教育施設)マネージメントを学ぶ為、日本語学校・専門学校・大学の教職員を経て、現在は日本語学校の学校長として運営管理にたずさわる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。