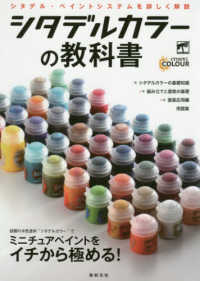出版社内容情報
好評「大阪古地図むかし案内」続編。明治~昭和初期の近代古地図を題材に、大阪の地誌や暮らしを探る。折込み古地図の付録つき。
明治~昭和初期の近代古地図を題材に、大阪の地誌や暮らしを探る案内書。俯瞰図と細部拡大図の両方から謎解きを試みる「読み解きスタイル」という独自の趣向で、見応えと読み応えを兼ね備えた構成とする。市街図から鉄道路線図、鳥瞰図(パノラマ図)、観光案内図まで、多種多彩な地図の細部を解読する面白さを味わいながら、大阪各地の歴史・地理・文化がわかる本。好評「大阪古地図むかし案内」の続編。折込み古地図の付録つき。
●前口上
◆第一章 怒涛の明治維新〈明治前期〉
第一図 新雕大坂細見全図(明治十六年〈一八八三〉) 明治のはじめ、四つの区があった
明治十六年の梅田ステーション
明治の大阪の象徴
学校の転変に見る明治
街のかたちが変わった
市制公布前夜の大阪
第二図 御免遊女町松嶋廓之図(明治元年〈一八六八〉) 近代大阪最大の遊廓の計画図
居留地対策としての松島遊廓開設
目論見はずれる
祭りと芸能と戦争と
遊廓計画図が語るもの
松島の四季
閑話一 工業都市の産声 大阪府重要工産地図(明治二十年頃)
◆第二章 博覧会と人力車のころ〈明治後期〉
第一図 大阪市と博覧会全地図 明治三十六年(一九〇三) 博覧会に五百三十万人
二十世紀のはじめに
博覧会が描いた近未来の生活
第五回内国勧業博覧会見聞録
第二図 大阪市街図附人力車賃金表(明治三十五年〈一九〇二〉) 人力車が地図の主役になった
人力車、いちばん身近な近代風景
爆発的な普及で庶民の足に
賃金表が語る車夫という職業
明治のもうひとつの顔
人力車でめぐる大阪名所
巡航船との乗客争奪戦
第三図 古今対照大阪市街地図(明治四十一年〈一九〇八〉) 古代・中世・現在にまたがる時間地図
古代の上町台地を彩るもの
千七百年前と今をつなぐ
中世の大阪へ
星と鉾流しと天神祭
明治の大阪と秀吉の影
鉄道地図が塗り変わった明治三十九年
閑話二 築港図に見る時代の転換 明治三十年築港着手当時之図
◆第三章 市電にゆられ新名所遊覧〈大正時代〉
第一図 大阪市内外電車便覧 電車系統線入大阪市街地図(大正九年〈一九二〇〉) 市電網が地図を塗り変えた日
市電開通と近代化の加速
市電が生んだ四ツ橋筋
「電車町程表一覧」が語る市電の時代
市電唱歌の近代風景
第二図 大阪遊覧案内地図〔裏面・京都名勝遊覧図〕(大正十一年〈一九二二〉) 交通網が四通八達、遊覧時代の地図
中心がいくつもある関西遊覧圏
聖天、天満宮、泉布観が北部の三名所
南北の「御堂」はじめ中部は歴史の色濃く
新旧が渾然となった「天王寺公園」が南部の顔
遊覧所の起点がなぜ四ツ橋なのか
「大阪市区改正設計」が意味するもの
閑話三 裏面が面白い地図 大阪案内地図 楽天地案内及高野山總本山指定旅館
内容説明
明治~昭和初期の近代古地図を題材に、「読み解きスタイル」という見応えと読み応えを兼ね備えた独自の趣向で、大阪の地誌や暮らしを探る案内書。市街図から鉄道路線図、パノラマ図、観光案内図まで、多種多彩な地図の細部を解読する面白さを味わいながら、大阪各地の歴史・地理・文化がわかる本。折込み古地図の付録つき。
目次
第1章 怒涛の明治維新―明治前期(新雕大坂細見全図(明治十六年(一八八三))―明治のはじめ、四つの区があった
御免遊女町松嶋廓之図(明治元年(一八六八))―近代大阪最大の遊廓の計画図)
第2章 博覧会と人力車のころ―明治後期(大阪市と博覧会全地図(明治三十六年(一九〇三))―博覧会に五百三十万人
大阪市街図附人力車賃金表(明治三十五年(一九〇二))―人力車が地図の主役になった ほか)
第3章 市電にゆられ新名所遊覧―大正時代(大阪市内外電車便覧電車系統線入大阪市街地図(大正九年(一九二〇))―市電網が地図を塗り変えた日
大阪遊覧案内地図―裏面・京都名勝遊覧図(大正十一年(一九二二))―交通網が四通八達、遊覧時代の地図)
第4章 大大阪パノラマの時代―大正末期~昭和初期(大大阪明細地図(大正十四年(一九二五))―大大阪誕生の瞬間をとらえる
御大典記念新版大阪府庁御認可グレート大阪市全図(昭和三年(一九二八))―昭和のグレート大阪を描く ほか)
第5章 近代古地図散策(大阪市街全図(発行年不明)―近代古地図、発行年を読み解く)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
saladin
狐狸窟彦兵衛
Osamu Imabeppu
わ!
-

- 和書
- まどから ぴょこっ!